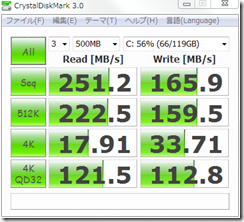3D対応ビデオプロジェクターSONY VPL-HW30ES

3DシンクロトランスミッターSONY TMR-PJ1

3Dプロジェクター用メガネSONY TDG-PJ1

【SANWASUPPLY】カテゴリ7フラットケーブル
(ブラック・5m) KB-FL7-05BK

トロン:レガシー 3Dスーパー・セット [Blu-ray]
後先考えずにやっちまいました。>VPL-HW30ES
発表を見た瞬間に購入自体は決意。この夏に買う予定だったんですが、車検があることを思い出し、2~3ヶ月先延ばしにすることに、、、したはずだったのが、AVACで今月いっぱい特価になってたのでつい…。Twitterには「手ぶらでAVAC離脱」と書いたのは、単に配送にしたって話だったとw。
■特徴
1.フルHD対応である
我が家の2台のプロジェクターは720p。テレビもフルHDではないので、そろそろフルHD出画デバイスが欲しいなぁというのは当然の流れ。
2.240Hz駆動、120Hzハイフレームレート対応である
最近の液晶テレビでは2倍速、4倍速が当たり前ですが、実はプロジェクターではあまり対応が進んでいません。BRAVIAのMotionFlowに感激してからすっかり信者になったσ(^^)としてはプロジェクターでも是非対応機種を買いたいと思っていました。しかし今までは70万円台~100万超えのモデルでしか対応しておらずとても手が出せないでいました。しかしこのHW30ESでついに30万円台前半という価格帯にMotionFlow機が降りてきてくれたのです。これはもう買うしかなワケです。
3. 3D対応である
4倍速表示できるということは(最低でも倍速表示が必要な)3D表示も余裕です。メガネとトランスミッターは別売りながらもバッチリ3Dに対応しています。
そんなHW30ESがAVACの円高差益還元セール(?)でメガネ、トランスミッター、LANケーブル(プロジェクターとトランスミッターを接続するのにCategory7のLANケーブルを使用)をセットにしてなお価格.com最安を下回るとのことで、都内の用事のついでに秋葉原のAVACに視聴に出かけ、本体だけでなんと30万を切る値段を提示されてうっかり特攻してしまったというワケです。
■予想を上回る感動
・80インチでのフルHDの解像感
ウチのスクリーンは80インチなので、720p->1080pにアップグレードしてもそんなに解像度感はかわらないんじゃないかなー、と思ってました。以前100万超の機種を視聴しに行った時も今回もAVAC店員さんには「80インチでも違いは明確」と言われつつも、彼らも商売だしなーとか半信半疑でした。だがしかしここでAVACさんに謝罪しなければなりません。80インチでもハッキリ違います!考えてみればテレビが37インチ位からフルHDの恩恵があるって言われてるんだから当たり前っちゃ当たり前なのかも。特にアニメとかCG映画の輪郭線はスゴいですね。元々そんなにジャギー感があったワケではないんですが、なにかが違います。「解像”感”」という他ありません。
・MotionFlow
ヌルヌルです。特に背景がスクロールするような場面で主体と背景のディスクリート感というか立体感というか、病みつきの滑らかさです。好みもあるでしょうが、フィルムの質感よりビデオ撮りの滑らかさが好きって人にはオススメです。
ただ相変わらず細かいところでたまに誤爆が発生してノイズが見えます。強/弱/切の3段階で、弱にすれば若干マシになるんですが、その分滑らかさも目減りします。どちらかを妥協しなければならないのは残念ですね。ソフト更新とかで更新されないですかねぇ。
・3D
店頭でAVATARを見た時はそれほどでもなかったんですが、一緒に買って来たTRON LAGACYはかなり自然でイイカンジの立体感があります。グラスは旧モデルよりも軽くなったせいか少し違和感減ったかな?ただ目はやっぱり疲れるかも。結局TRON LEGACY1本最後まで見られずに中断しちゃいました(単に眠かったせいもあるんですが)。実家のBRAVIA用のメガネはコイン電池だったのに対し、TDG-PJ1はmicroUSB端子による充電式になったのはナイスです。ちなみに充電器はプロジェクター本体に付属してました(メガネを複数買うことを思うと妥当な配慮ですね)。ちなみにメガネもトランスミッターも互換性がなく、当初実家で誰も使ってないから持って来ちゃうかという目論見は崩れ去りました。
明るさと制御の進歩で上位機種のHW90ESよりもクロストーク(反対側の目の映像が混ざって見えてしまいブレる現象)が大幅に減っているというフレコミですが、確かにBlu-ray 3Dのコンテンツでそれを感じることはありませんでした。一方サイドバイサイド収録のものは若干輪郭にブレが見えました。
あと、我が家のAVアンプ(SONY TA-DA3200ES)のHDMI端子は3Dパススルーに非対応なので、PS3->3200ES->HW30ESとつなぐとPS3側で3D対応ディスプレイを検出できず3Dに切り替わりません(サイドバイサイドはOK)。3200ESは最新のロスレス音声形式にも非対応だし、そろそろ買い換えたいところですが、HW30ES自体やや無謀な買い物だったので今しばらくは我慢ですね。当面はPS3->HW30ESをHDMIで直結し、音声はPS3->3200ESへ光デジタルでつなぐ(DTS止まり)という方法で凌ぐしかないっぽいです。HDMI出力が2系統あるお手頃なプレーヤーでもあるといいんですけど。本当はCREAS Pro付きで安いめのBDZ-AX1000を流通在庫があるうちに狙いたいところですが、AVアンプよりも高くなってしまうというw。CREAS Pro + HDMIx2なBDプレーヤー出ないですかねぇ。
・リモコン
デカいです。ただ画質モードや各種画像調節がダイレクトキーですぐに切り替えられる点は便利。例えばMotionFlowも専用ボタンがあって、押す度に切->弱->強のように切り替わるので、OSDで画面が隠れることもほとんどなく映像を見ながら色々試せる感じです。色々調整を追い込みたい時は重宝します。しばらくしてほとんど調整いじらなくなったら学習リモコンに必要なボタン信号だけ移して使うことになりそう。
・騒音
XV-Z3000は打ち上げ気味の設計でレンズシフトもなかったので、比較的低いポジションに設置してあり、カウチに座った時の頭の位置から近い目だったのに対し、HW30ESは比較的真正面への投射ポジションなのでラックの棚板を少し高い位置にしました。そのせいもあるかも知れませんが、視聴中の動作ノイズはまったく気になりません。コンテンツが無音の時には多少聞こえますが、むしろ初代PS3等の方が遥かにうるさいので、基本的にプロジェクターの音は完全にかき消されている感じです。また視聴が終わって電源を切った後にしばらくファン全開でランプを冷やすのが一般的ですが、本機はその間の音もほとんど聞こえないですね。まるでLEDライドを使った機種のようです。
個人的にはちょっと思い切った買い物でしたが、コストパフォーマンスはとんでもなく高い名機だと思います。今年のVGPとか席巻するんじゃないでしょうか。この上さらにBlu-rayソフトをガンガン買ってしまいそうで恐いです。
■XV-Z3000は寝室へ、TH-AE500はどうしよう…
メイン機を引退したSHARP XV-Z3000(2006年購入)は主にゲームに使用する寝室用に転用しました。寝室で使ってたPanasonic TH-AE500も先日ランプ交換したばかりでまだまだ使えるんですが、こちらは完全な720pパネル。Z3000はDLPなのもあってか珍しい1280×768。XGAも含め縦768がDbD表示できるのはPCで使うには地味に便利だったりするんですよね。
TH-AE500はどうしようかなぁ。HDMIがついてないからヤフオクに出してもあまり値がつかないかもなー。