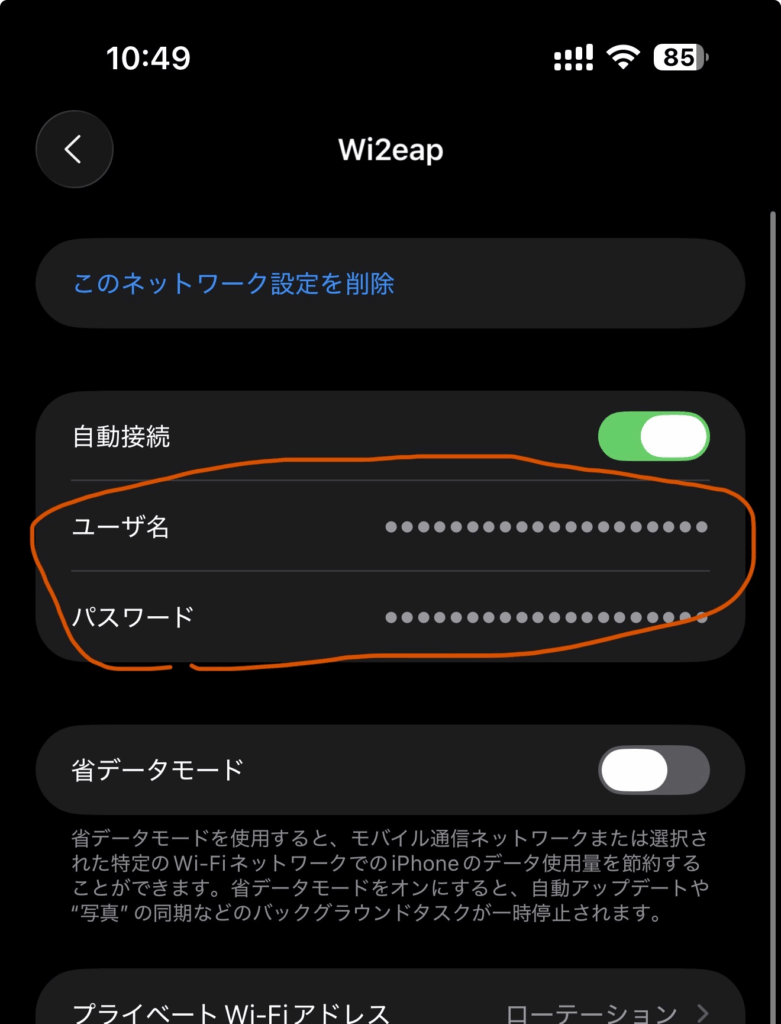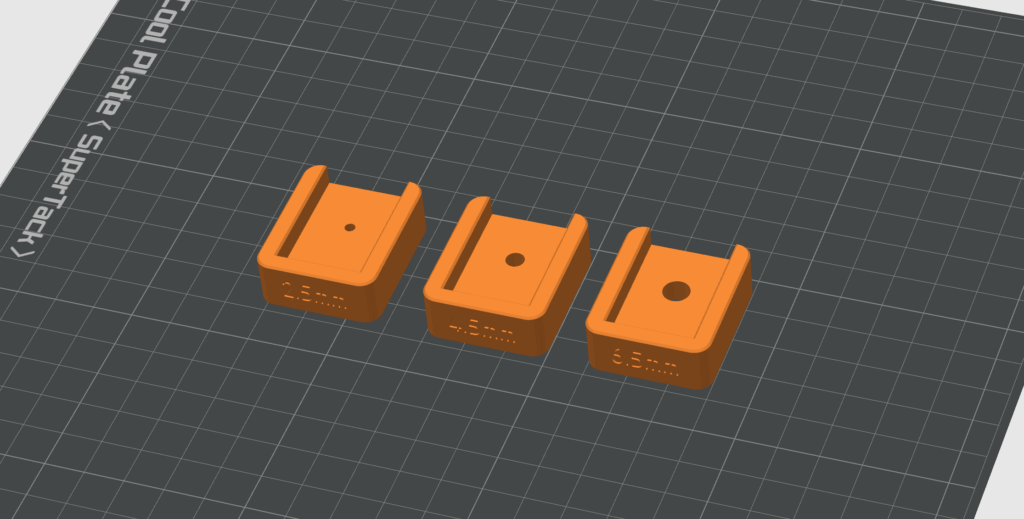元祖Arm64 Windows版のSurface Pro X(SQ1)がブートしなくなって半年あまり。ついにATOKがArm版Windowsに対応したということで重い腰を上げて復活させることにしました。
症状
なにかしらのタイミングでシステムファイルが壊れたらしく、Windowsが起動せず青画面の自動回復モードに突入するようになりました。ここでは回復キーの入力を求められ、それは突破するも結局エラーで回復できないという流れ。それ以外の修復やロールバックも全てエラーという感じで、完全初期化しかないという形。
公式手順に従うが…
公式手順はこちら。要約すると、
- 上記ページでモデル名とシリアルNo.を入力し、回復イメージのzipファイルをダウンロードする(本記事執筆時点で、24H2、23H2、22H2、20H2が選択可能)
- Windows上で「回復ドライブ」ツールを使ってUSBフラッシュメモリに回復ドライブを作成する(この時、「システムファイルを回復ドライブにバックアップします。」のチェックを外す)
- できたUSBフラッシュメモリドライブに、回復イメージzipの中身をコピーし、存在するファイルは全て上書きする
- Surfaceをシャットダウンした状態でUSBフラッシュメモリを挿し、他のUSBデバイスは全て外す
- 音量下げボタンを押しながら電源ボタンを押しで電源を入れる
- 黒画面に白のWindowsロゴが出たら(つまり電源が入ったら)電源ボタンを離す
- グルグルが出たら音量下ボタンも離す
これでUSBブートして言語選択画面になるはず、、だけど何度やってもならない。念のため、5以降のかわりに音量上ボタンをつかいUFEI管理画面に入り、ブートデバイスでUSB Driveを選んで右スワイプし、「Immidiatelyなんちゃら(今すぐUSBブートする的な項目)」からしてもダメ。
24H2イメージがおかしい。23H2ならあっさり成功
散々あれこれ試した挙げ句の結論として、「24H2イメージが壊れている」というのが濃厚です。海外のMSサポート掲示板でも報告がありました。23H2イメージでやりなおしたら一発で成功。
しかし23H2はサポート終了してて24H2アップデートも降ってこない
ようやくWindows 11 23H2は起動しました。そこからせこせこWindows Updateをかけてこうとするものの、23H2の最新にまではなるものの24H2が降ってこない。Windows Update画面で「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」をオンにしたり、Surfaceのドライバーやファームウェアをチェックしてみてもダメ。Gemini曰く23H2がサポート終了しているためアップデーターの配布もされてないと(そんなことある?)。
ならばWindows 11 インストール アシスタントをダウンロードして実行すればいいかと思ってやってみると、なんと「Arm64は対応してない」というエラーで起動せず。詰んだ?
Windows 11 ISOイメージからアップデート
またさらにGemini/ChatGPTと相談した結果、ISOイメージをマウントして中にあるsetup.exeを実行すれば良いということ。Arm64版のWindows11 ISOイメージはこちらで配布されています。幸い最新の25H2が置いてあるので24H2はスキップすることができました。
USBメモリだと遅そうなので、ISOファイルを本体SSDにコピーし、右クリックメニューから「プログラムで開く」→Explorerを選ぶとマウントできます。DVDに焼く必要なし。便利になったもんです。その中のsetup.exeを実行してインストールできました。
やれやれなのらね。
まとめ
今後、24H2イメージが修正されたり、25H2イメージが配布されたりという可能性もありますが、Pro Xはもう数年前のモデルだしあまりサポートは期待できないかも知れません。
とりあえずの手順としては、
- 23H2バージョンの回復イメージを公式手順で作成する(別PCからでもOK)
- それを使って23H2状態のWindows11までリカバリー
- 25H2のISOイメージをダウンロードしてマウント
- 中のsetup.exeを実行して更新
というのが最短手順になる気がします。なおこの際、ユーザーファイルは完全に消えるのでご注意ください。