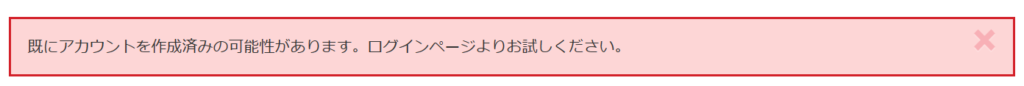長期試用してから記事を仕上げて公開しようと思い、丸一ヶ月も寝かせてしまいました。この記事は2024年1月4日頃に90%くらいまで書いて、ひと月後の今日ようやく仕上げて公開しています。
明けましておめでとうございます。初買いしました。新製品ではないですが、Apple傘下のヘッドフォン/イヤホンブランドBeatsのFit Proです。
昨年末に近所で発見したchocoZAPに通い始め、AirPods Proで動画の音声を聞きながらトレッドミル(ルームランナー)で走ったり(実際には早歩きレベルですが便宜上”走る”と表現しますw)してると、これがまぁ落ちる落ちる。トレッドミル中にハズれてキャッチしそこねると、高速で動いているベルト部分に弾き飛ばされて遠くまですっ飛んでしまうこともありますし、動いているトレッドミルから降りたり乗ったりも危ないしで避けたいです。イヤーチップを落ちにくいと言われるものに交換しても多少マシにはなるものの、やはり長時間の振動でズレてきて、時折グイっと指で押し込み直す必要がありストレスでした。
そこでスポーツ用途を意識して、より外れにくいヘッドフォン/イヤホンを買いたいなと。要件としては、
- ラン中にとにかく外れて落ちない
- アクティブノイズキャンセリング(トレッドミル等の器具の作動音などはキャンセルしたい)
- できればApple/Beats製のH1チップ搭載機(Appleデバイスとの相性が◎)
音楽よりは動画視聴がメインになると思うので音質はそこまで気にせず。iPhoneかiPadがメイン親機になると思うのでLDACなどのコーデックも優先度低。遅延に関してはAirPods Proで特に不満はなかったのでH1チップのものなら大丈夫だろうなという予想。
また最近は自宅リビングダイニングで作業や料理をしてる時に、テレビ+AppleTVで動画を流してAirPods Proで聴いたりしがち。この時も包丁もってタマネギ刻んでる最中にAirPods Proがポロっと落ちると非常に問題です。こういう時もH1の再接続機能でさくっと使い回しできるといいなと。
そんなこんなでAppleまたはBeats製品群のどれかがいいかなーと。
ただやはり汗をかくのでイヤーパッドで耳を覆うAirPods Proのようなオーバーイヤーヘッドフォンは除外。ANCのない無印AirPodsも除外。Vision Proを見越してAirPods ProのUSB-Cバージョンも気にはなっているものの、とりあえずジム用に初Beatsいってみるかと。あとBeatsはAirPodsシリーズよりも先行してUSB-C化が進んでいる点も後押しになりました。
まずスポーツにヨサゲなのは、FlexですがこちらはANCがなし。また「ハズれても落ちないので安心」ではあるけど「外れない」かどうかでいうと疑問が残ります。
次はPowerbeats Pro。ANDあり。フックタイプなのでもっとも耳から外れなさそう。ただ自分はメガネerなので、干渉はまた別のストレスにもなりそうで躊躇。また充電ケースがLightningで値段も少々お高め。今からこの値段出して買うのもなぁ、と思ってしまった。
そして最後はFit Pro。まぁタイトル通り結局こちらにしたわけですが、ANCあり、USB-C充電とスペックは申し分なし。そして保持性能としてはウイングチップと呼ばれる角が生えた形状のチップを採用するタイプ。Boseとかにあるイメージ。これでしっかり保持できるならばメガネとの干渉も気にならずよさげ。
年明けにヨドバシ詣かApple Store詣をして装着感やカラーを確かめたてみようかなと思ってたんですが、Appleの初売り対象になっていたので通販で特攻してしまいました。ちなみに定価の28,800円から6,000円分のAppleギフト還元。価格.comの最安で2万ぽっきりくらいのところがあったので、そっちの方が安いかと思ったんですが、まぁ辰年デザインのAirTagが1つもらえるなら実質お得かなと思い初売りで注文、その後でAirTagはiPhone買った人だけと気付いてガックシ。まぁ新年でも1日で届いたのでヨシ。
■ファーストインプレ
事前に読んでたレビュー通り、
- AirPodsより低音が豊か
- ANCは同等レベル
という印象。ブーミーというほどではなく慣れれば特に違和感なく動画を見てられますし、迫力もあります。
そして期待の落ちにくさですが今のところ一度も不意に落ちたこともなくトレッドミルも安心してやれています。これとXREAL Airで壁にAR投影した感じでアニメをみながら有酸素運動するのがマイブーム。
バッテリーが切れるほど連続使用したことはないですが、普通に使い終わったらケースに戻しておけば使いたい時には満タンになってる印象。ケースの充電はたまに思い出した時にやる程度です。限界使用しての印象ではないですがAirPods Proよりも持つイメージ。
唯一惜しいのは「探す」アプリでUWBで近距離検索ができない点くらい。「探す」自体には対応しています。近距離探索時に方向と距離が出ない。AirPods Proの初代と同じ仕様です。
■まとめ
期待通り、落下の不安なくジム通いができていて満足度が高いです。ジム以外で普通に装着して家事などしていてもAirPods Proより遥かにに安心感があり常用したいのはこちらです。
iPhoneやMacなどのAppleデバイスで使う場合の接続切り替えの手軽さ/素早さはAirPodsシリーズ同等で隙がなく、もっと評価されてよい製品だと思います。
UWBに対応した新モデルで良いカラーがあれば買い換えてしまうかも知れません。いずれVision Proが買えるようになったらロスレス対応のAirPods Pro第二世代(USB-Cバージョン)に買い換えないとと思ってましたが、できればそれまでにこちらがアップデートして同等性能になってほしいものです。








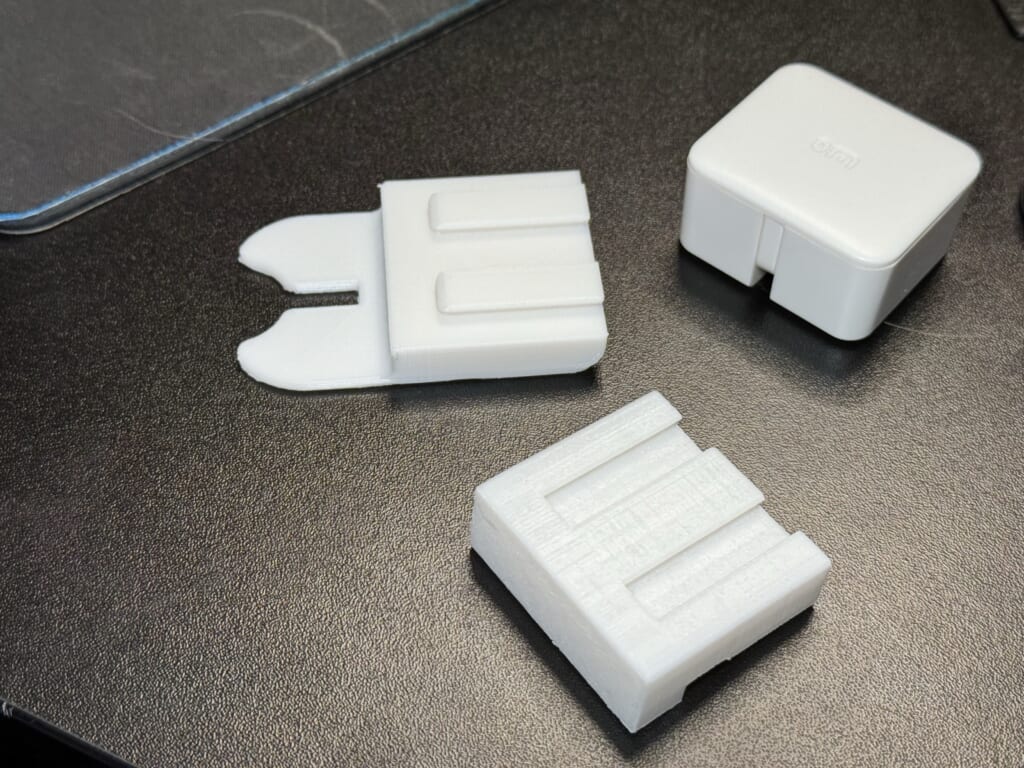
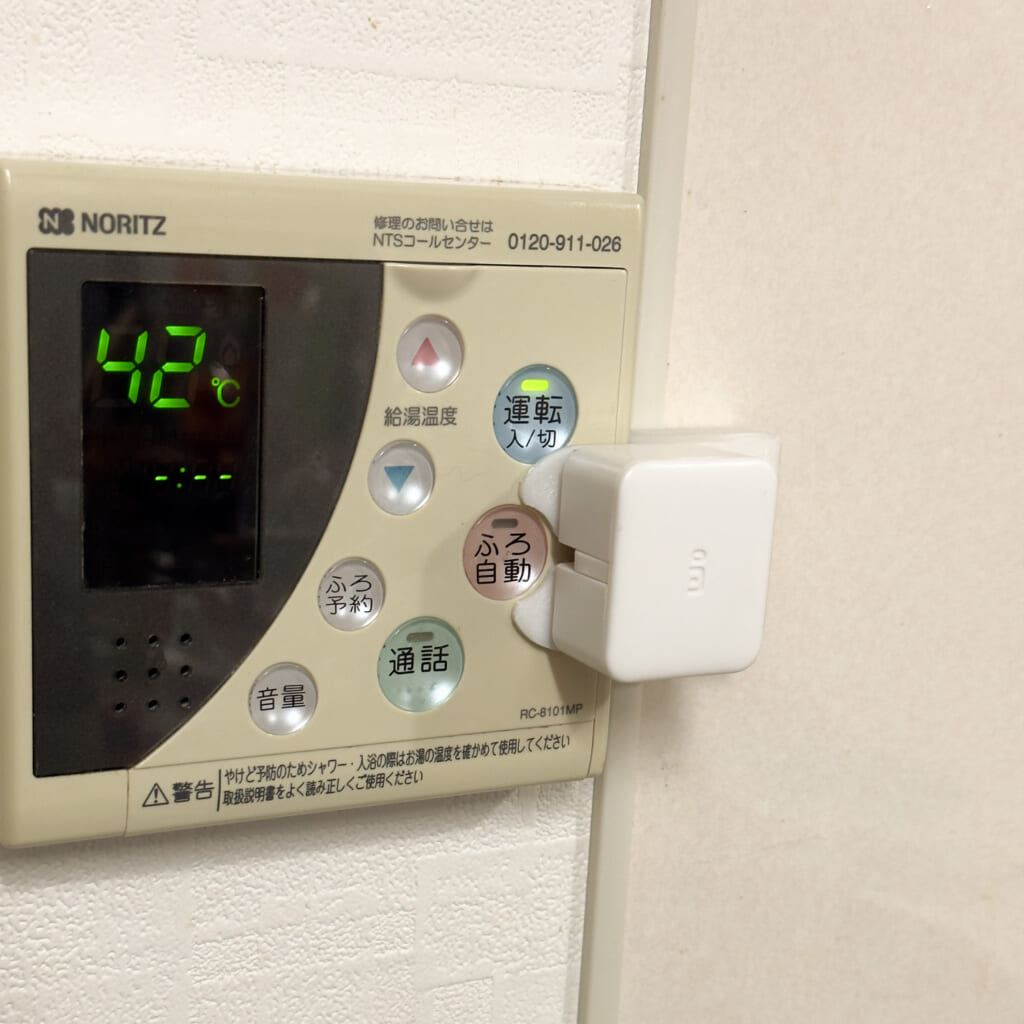

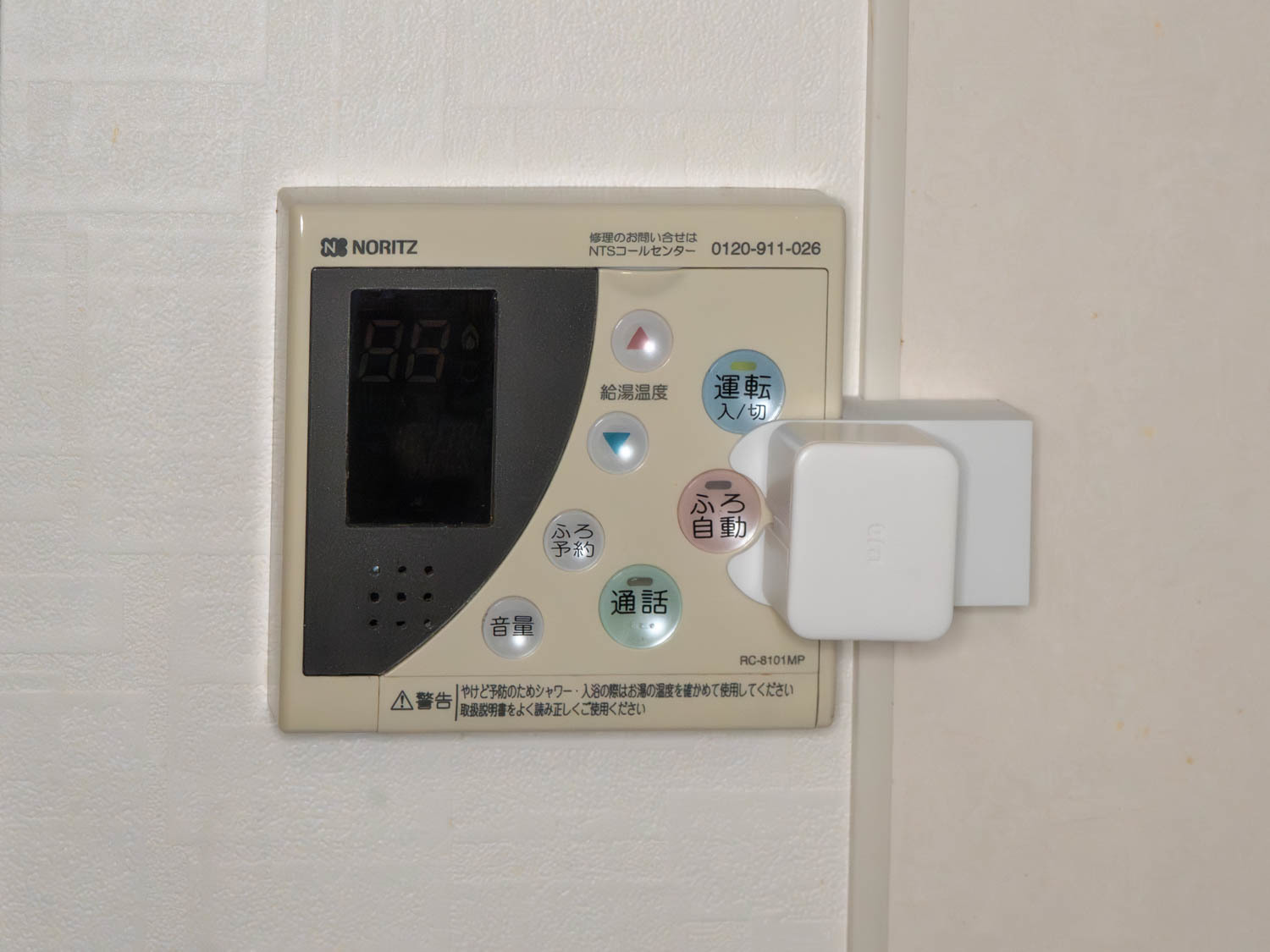
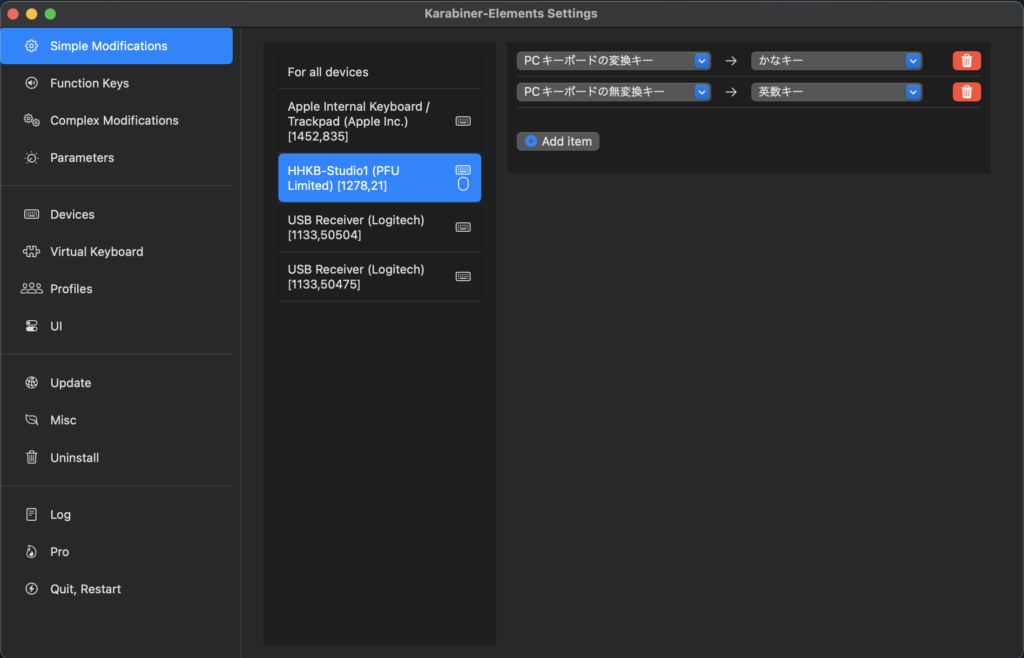



![SanDisk ( サンディスク ) 256GB Extreme microSDXC A2 SDSQXA1-256G [ 海外パッケージ ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41NKkAkE8iL._SL500_.jpg)