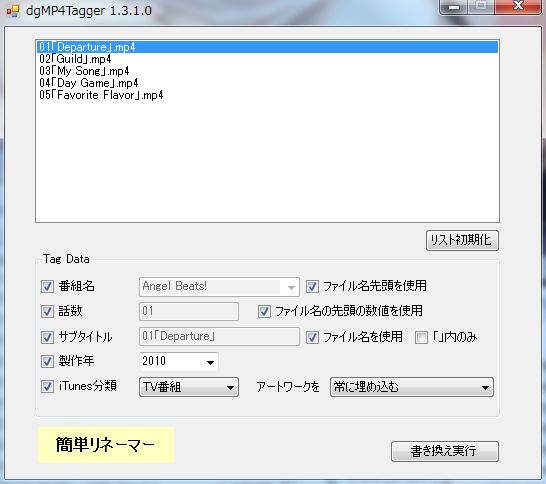iOSプログラミングに慣れてきて当然実機で動かしてみたくなります。早速有償のiOS Developer Programに登録申請してみました。
がこのフローがヒドい。友人からの事前情報で、Apple IDに日本語が含まれているとアクティベーションにコケて、メールで修正依頼をしたりして長いこと待たされることがわかってたので、色々ググってみました。要約すると、
- Apple IDの登録情報に2バイト文字があるとアクティベーションに失敗する
- 逆にすべて英語だと日本のApple Storeでの決済手続きがエラーになる
もうこれだけでもヒドい話です。どうしてこんな簡単な問題が何年も放置されてるんでしょうね?
なんとか問い合わせ手続きしなくて済むようにと、先人達の記録を参考に、開発専用の新規Apple IDを取得してすべて英語で記入するところから始めてみました。開発者申請のページから新規にApple IDを登録するとこから始める選択肢があるのでそれを使います。メール認証をして登録完了。続けて有償ライセンスの購入に進むと、カートにライセンスが入った状態で日本のApple Store画面にリダイレクトされます。そのまま決済に進むと、名前や住所を日本語で入れ直すよう促されます。これで無事決済は完了。午前零時前後に手続きしたところ、数時間後の翌朝6時半くらいにアクティベーションコードがメールで届きました。
が、結局お約束のエラー!
新しくApple IDとった意味なし。愚痴をたれつつも、エラー画面内の「Contact Us」というリンクから行ける問い合わせフォームで連絡。こちらからアクションを起こさない限り向こうはなにもしてくれないそうなので。で、最短で手続きが進む様に、あらかじめネットで調べて必要事項(Apple Storeの注文履歴画面から、
- 『ご請求、ご連絡先』
- 注文番号 (W+数字8桁)
をコピペ。またメールにあったEnrollment IDも添えて送信したのが朝9時。返事が来たのが午後2時過ぎ(日本語)。あろうことか、上記の情報を知らせろと書いてきています。だからコピペしたでしょ?とメールに添付されたフォーム記入文面を見る。なんと、
2バイト文字が全て抜け落ちてます。
コピペした「We are unable to activate」というエラーメッセージ、住所の中の部屋番号と番地と郵便番号、注文番号、Enrollment IDという英数字のみの意味不明な送信文です。おそらくエラーメッセージから問い合わせ内容を類推して返信してきてるんでしょう。
日本語入れると全部抜かれて送られるフォームなんてナナメ上過ぎ。
これまた知人から「Appleは開発者に優しくない会社」と聞いてましたが、確かにその通りかも。あるいは非1バイト文字圏軽視しすぎ。
結論としては、「一発申請は不可能。あれこれ悩むより余裕もって申請して、さっさとエラー出してContact Usから連絡。RegionにJapanを選択し、上記エラーメッセージさえ貼り付けておけば用件は通る。日本語は書いても無駄。詳細はその後のメールへの返信で記入」ってとこですかね。もしかするとContact Usフォームに請求、連絡先情報を英語表記にして貼ればいいのかも知れませんが、たぶんApple Storeの表示とマッチしないとNG食らう気がします。