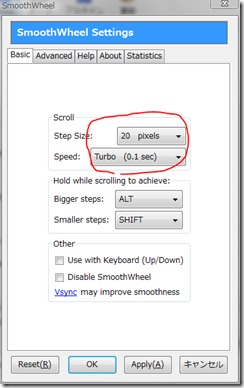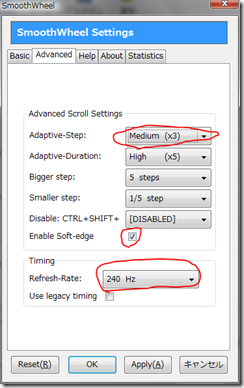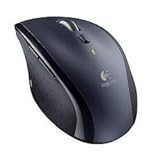12月頭にNECの新型WiMAXルーターWM3500Rを入手してました。即解前提で買うのはあまり好きではないので定価覚悟でヤマダに行ったらむしろ白ロム販売はしてないので、契約付きで買って一ヶ月以内に解約してくれとのこと。店員が推奨するならまぁいいやってことで2,800円で購入。一ヶ月分の通信費を払っても数千円でゲット。一ヶ月以内の解約なら違約金も発生せず、ってことで一ヶ月使用した上で、先日解約手続き。電話はなかなかつながらずでしたが、つながった後は契約ID行っただけで理由を聞かれることもなく手続き完了。解約殺到でいちいち会話してられないって雰囲気でしたw。
さて、元々のDIS WiMAXでの契約では、VAIO type Z、VAIO P、MW-U2510 (+Uload-5000)で枠はいっぱい。どれかを解約しなければなりません。MW-U2510単体でMacBook Airでも使えるし、使用頻度から行けばVAIO Pを削った方がよかったんですが、やはり最軽量装備としてVAIO P単体でネットできる状態は維持しておきたかったのでMW-U2510を登録解除。かわりにWM3500Rを組み入れました。
せっかくなので比較ベンチ。ただし感度は中程度の室内にて、MacBook Air 11’を使用。
・MW-U2510
・WM3500R (Wi-Fi)

・WM3500R (USB)


USB直結のMW-U2510が下りは最速だったんですが、なぜか上りがヒドいことに。WM3500RのWi-Fi接続はボチボチ?でWi-Fiに比べて速くなると噂のUSB直結ですが、本体の位置に束縛されて窓から離れることで、感度が中から低に落ちてむしろ遅くなる結果に。2つ目はMacごと窓際によって最測定したもの。実使用ではあまり意味のない数値です。
この結果だけみるとWi-Fiがバランスよく使える感じではありますが、もう少し電波のよいところでも測定してみたいですね。
ちなみにOSXでUSB直結モードをする場合、全く設定なしで接続できるので使用感は悪くないです。最近はSONY “Reader”などmicroUSBデバイスが増えてケーブルも常時携帯するようになってるので、速度が必要な時は適宜USB直結を活用するのもありなんじゃないかなと。