最近のホテルには普通にWi-Fiが完備されていて、それにつなげばインターネットには出られますが、私はマイルーターを持ち込みます。SIMカードが入るモバイルルーターではなく、ホテルの有線またはWi-Fiネットワークを使いつつ、独自にネットワークを作りWi-Fi電波を飛ばすタイプのルーター(ここではホテルルーターと呼びます)製品です。
理由はいくつかあって、
- 持ち込む機器がたくさんあり個別にホテルWi-Fiの設定をするのが面倒。自宅のWi-Fi設定のまま接続できると便利。
- ホテルのWi-Fi設備の規格が古いと損した気になる。できるだけ有線に近い最高速度で使いたい。
- 持ち込んだ機器同士で自由に通信できるローカルネットワークを構築したい。
などです。仕事でひとりで止まる時でも、ノートPC 2台、スマホ2台、iPad、Meta Quest2、Amazon FireTVくらいは持ち込みますし、同居人も持参デバイスが多い方です。もうSSIDの方を自宅に揃えちゃう方が楽なのです。またPC上のコンテンツをQuest2やFireTVで再生しようなんてことをすると、ローカル通信がブロックされないことや速度が出ることも重要です。
■GL iNet一択?
ホテルルーターの要件としては、
- WAN側が有線とWi-Fi両方対応していると柔軟性が高い
- 小型で持ち運びが楽
- 電源がUSBで取れると専用ACアダプタ不要で荷物が減る
という辺りでしょうか。ホテルによって有線があるところとWi-Fiオンリーなところがありますが、もし有線があるならそちらを使いたいものです。個人的には最後のUSB電源であることも重視。どのみちマルチポートのUSB充電器やケーブルは色々持っていくのでそれで済ませたい。
ただこれらは性能と相反する要素で、できるだけ小さく、USB 5Vで駆動でき、とするとWi-Fi性能は低かったり有線ポートも減らされたりしがち。
そして「ホテルのWi-Fiでいいじゃん」って人が大半でしょうから各社ともあまり積極的にこのカテゴリの開発を進めてない気がします。例えばBUFFALOだと2019年に出たWMR-433W2が最新。11ac(Wi-Fi5)にはかろうじて対応しているものの、433MHz止まり。有線ポートも100Mbpsが1つだけで有線->有線のルーティングはできません。
これだったらそれこそホテルのWi-Fiに直接つないだ方がマシじゃないかってレベルでしょう。
そんな中で頑張っているのが海外(香港?)メーカーのGL.iNetです。実はここのホテルルーター製品を買うのは3台目。
最初がGL-AR750S(ペットネームSlate)。
GL.iNet GL-AR750S-Ext ギガビット 無線LAN WiFi vpnトラベルルーター 11ac/n/g/b/a 300Mbps(2.4G)+433Mbps…
Wi-Fi規格はBUFFALOと同じ5GHzで433Mbpsですが有線がWAN/LAN完備で1Gbpsでした。これが電源コネクタの接触不良か電源が勝手に切れるようになり、次の買い換えたのはGL-MT1300 (同Beryl)。
5GHzが867Mbpsにアップ。電源ポートがUSB-Cになりました。電源投入後、起動して電波が跳ぶまでの時間が「あれ?」って思うくらい遅いのが気になりましたが、どうせ滞在中は入れっぱなしだし概ね満足していました。
下の今回購入の最新モデル含め、共通機能としては、
- 有線WAN x1、有線LAN x2
- WAN側は有線、Wi-Fiに加えUSBテザリングも対応。iPhoneの高速回線を内蔵テザリングよりマシな条件で共有可能。
- オープンソースのOpenWRTというLinuxベースのルーターを拡張して作られており、豊富な拡張が可能。
- VPNサーバーを搭載しているが、相変わらずL2TPなどスマホと相性の良いものは非対応。
- Beryl以降はUSB-C電源駆動
■Wi-Fi6対応モデル登場!
そして今回購入したのがGL-AXT1800(ペットネームはSlate AX)です。外観はBerylの色違いという感じですが色のせいかSlate(屋根瓦)にWi-Fi6(802.11ax)を示すであろうAXをつけた感じになっています。
GL.iNet GL-AXT1800(Slate AX) WiFiルーターWiFi6 無線LAN VPN トラベル デュアルバンド 11 b/g/n/ac/ax 12…
そう、Wi-Fi6に対応し5GHzで1,200Mbpsに対応しました。果たしてホテルのWAN条件的、Wi-Fiチャンネル空き状況的に実効性のある速度差が出るかはなんともですが、UT現場やセミナーなどに提供したりもするので、少しでも余力があり安定動作するなら投資価値はあるだろうと。
実はまさにホテルに滞在している時にふと「新型出たかな?」と検索して知って、その場でホテル宛てに注文。しかしAmazonの配送遅延を喰らいチェックアウト日の受け取りとなってしまった為、まだ実際のホテル環境でテストができていません。今回は簡単なファーストインプレのみ。
・微妙に大きくなった外観

今まで使用していたBerylと並べて撮ってみました。写真だけみて購入したのでてっきり中身だけアップデートしたイメージでしたが、筐体も少しだけ大型化していました。並べなければ忘れてしまうような違いですが、ちょっとだけショック。
またフロントの動作ランプが小型化し、下向き(トップカバー側は切り欠きがなく被さってる感じ)に変更され、眩しさが軽減したかなと思います。正直Berylはホテルで就寝時ちょっと気になってたので、これは歓迎。
ビルドクオリティは特別高くもないですがまぁルーターとしては普通。Berylはちょっとガジェットぽくない水色でしたが、Slate AXはまぁ普通のダークグレーという感じ。

重ねてみました。一回り大きくなったのがわかりますでしょうか?まぁこれでも一般的な家庭据置用Wi-Fi6ルーターよりは全然小さいのでアリなんですが。

背面のポートは微妙に配置が逆順になっています。WANポートが一番外側なのは同じ。

なんと底面を覗くと冷却ファンが見えました(左はヒートシンク?)。Wi-Fi6/1,200Mbpsの負荷を処理するにはやはり発熱量が大きいんでしょうか。まだそれほど負荷をかけていませんが、とりあえず(故障してなければw)アイドリング時は回転しないようです。ただそれだけにトップカバーは結構温かい状態です。ヤケドするレベルでないですが、カイロ代わりに肌に当てるには熱すぎるというレベル。まぁ静かなのに越したことはないですが、基本触るものでもないので安定第一でしっかり冷やしてくれるならアリかなと思います。
ちなみにBerylは底面を見ても通気穴が狭く中にファンがあるかどうかは視認できません。少なくとも記憶にある限りは音が聞こえたことはない気がします。そこまで性能を求めず、静音性、コスパ、サイズを重視するなら今からであってもBerylを選択するのも手かも知れないですね。

付属ACアダプタは5V x 4Aで20Wタイプのものでした。コンセント形状を国ごとに付け替えできるタイプでやや大きめ。交換パーツは日本向けのもののみ付属。出張/旅行用なので荷物を減らしたい人はもっと小さくてコンセントのブレードが畳めるものが使いたいところです。例えばこれとか。
・管理画面がサクサク化
管理画面のデザインは基本的にBerylと同一ですが、全体的にレスポンス良く動くようになったなという印象。IPQ6000 1.2GHz クアッドコアプロセッサーのお陰なんでしょうか。
基本設定項目としては、
- 電波の強さはマックス/高/中/低の4段階。ホテルで使うだけなら相当に弱めても平気でしょう。
- 5GHz帯はDFS(法律で義務づけられた定期的に混信を防ぐためにチェック)を要するチャンネル(W53/56)を使っていいかON/OFFがあり、デフォルトOFFでW52だけが選べるようになっています。わかりやすいかも。
- 2.4GHz、5GHzそれぞれにメインのSSIDとゲスト用SSIDを設定可能。ちなみに有線LANはメイン側(192.168.8.0/24)に接続され、ゲスト側(192.168.9.0/24)で相互通信はできません。
- ちなみにWi-Fiの暗号化はWPA3まで対応していますがBerylの時になぜかiPhoneからつながらなくてWPA2-PSKに落としていました。
■まとめ
今月また仕事でホテル泊まり予定があるので、実使用レポートはその時に追記しようと思います。忘れなかったらBerylも持っていって速度比較などもできればなと。
ともあれ、国産メーカーが実質撤退したかというような気すらする希少なホテルルーターカテゴリでWi-Fi6対応モデルが出て嬉しく思います。活発に開発をしているGL.iNetのことなのでiPhone15?がWi-Fi 6Eに対応する頃にはまた新型が出てくれると期待して、それまでがっつり活用していこうと思います。












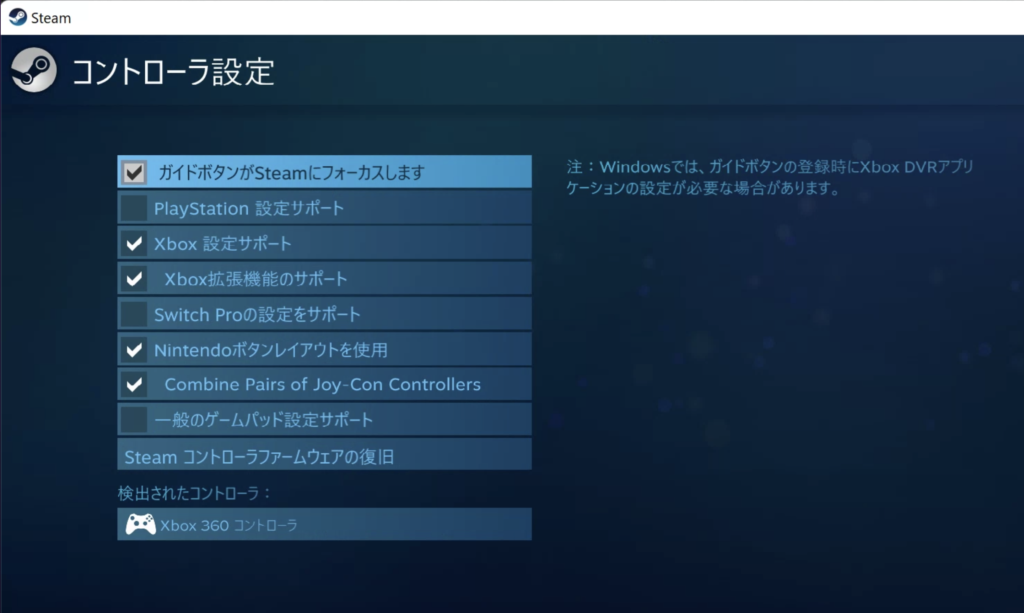
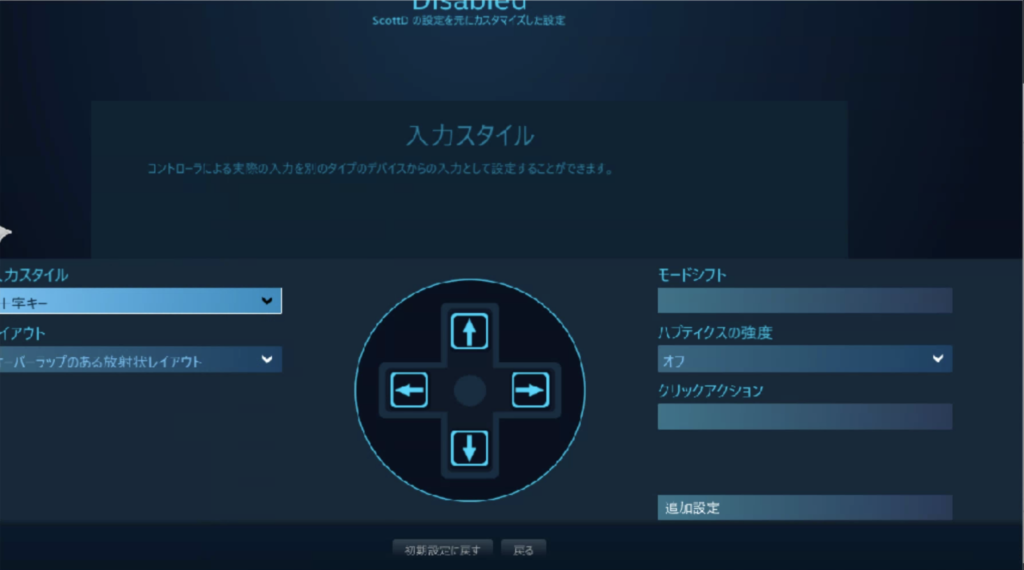
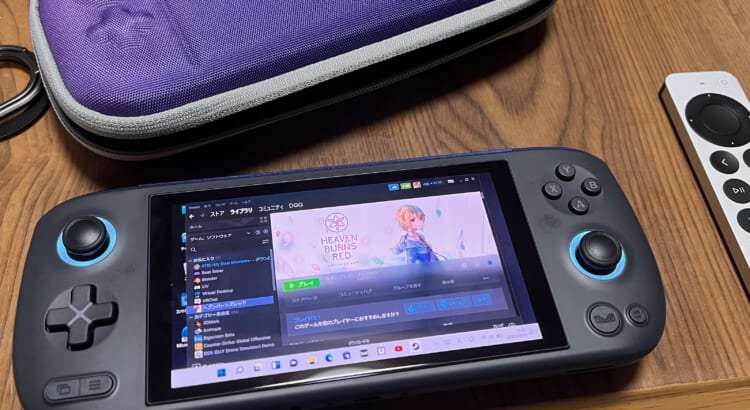



![シャープ 水なし自動調理鍋 ヘルシオ ホットクック KN-HW16G-W 無線LAN対応 ホワイト系 [1.6L]](https://m.media-amazon.com/images/I/31q+8AFRQBL._SL500_.jpg)

