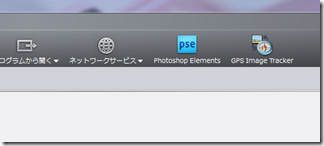PC録画環境もBDレコもある我が家ではさしたる必要性はなかったのですが、PS3パワーを駆使したレコーダーUIを体験してみたくてtorneを購入してみました。初回は逃したんですが、一昨日あたりにあちこち再入荷があったらしく、近所のGEOで10台ほど在庫有り状態で普通に買えました。
■torne UI所感
やはり家電レコーダーに比べると操作性は良いです。まずなによりレスポンスが良い。そしてSIX AXIS/Dual Shock 3を使った両手オペレーションが存外しっくりくる印象。BDリモコンよりも快適かも知れないです。実際、BDリモコンの専用ボタンはほとんど効きません。例えば15秒フラッシュボタンがあるのに動作せず、R1/L1ボタンは効く、って感じ。ここは追々バージョンアップで対応してくれると嬉しいですね。
ユーザビリティ的に微妙だなと思うのはトップ画面(メインメニュー)。全ての機能の入り口が等間隔で円形配置されていてクルクル回して選ぶ感じなんですが、SETTING(初期設定)やCONTROL(ボタン割り付け設定)みたいな普段使わないようなものまで同格で配置されていて日常の操作で無駄を感じます。またどれが何のボタンかもフォーカスしないとラベルが出ないので、とっさにどれを選ぶのか狙いがつかず、1つずつ回してラベル確認して「違った、次」と進めて行く感じ。通常のリスト形式だと位置を手がかりにして学習が進んだりするんですが、円形メニューだと毎回位置も変わってしまうので、純粋にアイコンの意味を記憶する必要があります。これは慣れれば(覚えれば)解消される可能性はありますが、ちょっとUXに走り過ぎちゃったんじゃね?という印象は否めません。
トップ画面以外は概ね良好で、少ないボタンでやりたいことができるよう上手くまとめてあると思います。Playstation Storeなどに慣れてる人なら違和感なく操作できるんじゃないでしょうか。
一方で機能的には必要最低限で、今時の家電レコに比べるとちょっと見劣りがします。W録とかBS/CSとかハード的な制限はおいといても、ソフト面で解決できる機能として、とりあえずEPG(電子番組表)画面で、特定のカテゴリを色分け表示する機能は欲しかったです。例えばσ(^^)の場合、アニメ、映画、ドキュメンタリーはよく見るけど、ドラマ、バラエティ、スポーツはほとんど用無しなので、はっきり視覚的に描き分けられてると番組表を見る効率が非常に高いです。また録った番組の一覧画面は予約別のフォルダ分け表示とかはなく、ズラーっと並んでソート順が選べる程度とシンプル。この辺は同じグループのBDレコーダーなどのノウハウを共有できないもんでしょうか。VerUpに期待。あと、録画パターンは一回、毎日、毎週の3つしかないんですが、月~金みたいなのはどうするんでしょうね?番組名でちゃんと認識して土日はスキップとかするんでしょうか?ちょっとWBSを予約して挙動を調べてみたいと思います。
■HDレコーダーとしての実用性はあるのか?
起動時間、操作を別にすれば、視聴用としてもそれなりに扱いやすいと思います。Bluetoothのコントローラー/リモコンは向きを意識しなくていいので便利ですしね。ので、地デジチューナーがついてないHDテレビ/モニタと組み合わせて使うのはアリかなと思います。ただ、それらのコントローラーで音量が調節できないのがかなり痛い。どうしてPS3側でもある程度は音量調整できるようにしてくれなかったんでしょうね。
またウチは初代の60GBモデルですが、録画動作中のファンの音は結構気になります。寝室で深夜番組を録るにはちょっとつらいです。そういう使い方をするなら薄型以降のモデルと組み合わせるのが前提かもです(薄型がどれくらい静かなのか自分の耳で確かめたことはないですが)。
普通にデジタルチューナーのついてるテレビにこれを組み合わせて使うメリットはあまりないかなぁ。リアルタイムの視聴率ゲージとかに価値を見いだせる人向け。あと、画面を2分割してブラウザを使える機能は面白いですが、文字入力パレットがど真ん中に出て映像を隠してしまうのは微妙。パレットも右側のブラウザエリアに納めるか、せめて寄せて欲しいです。これハードウェア的なキーボードをつけたらどうなるんだろ?テレビみながらWebで調べ物、という使い方はσ(^^)自身よくするのでアイデアとしてはおおいにアリだと思いますね。予約数ランキングは家電レコでも一部についてた時期がありますが、便利といえば便利ですね。ちょうど今みたいな改変期は予約入れ直しが多いですが、ランキングみるとすぐ見つかったり。PS3ということもあって、あきらかにアニメ好き層が多いランキングなので、個人的には実用性も高いw。
PSP連携機能は、SONY製レコーダーを既に持ってる我が家では今のとこあまり魅力を感じないです。転送時に変換する分、BDレコよりも時間がかかるようですし。リモートプレイもWANから使えるなら是非使いたい気はしますがLAN専用だとどうかなぁ。まぁお風呂では近々試してみたいと思います。
「BDも観られるゲーム機」から「BDも地デジみ観られて、レコーダーにもなるゲーム機」へとステップアップできるという点ではPS3の付加価値を上げる良い周辺機器だと思います。ほとんどテレビを観ない人、私室ユースにはとてもCP高い製品ですよね。
■ついでにHDDも換装してみました
レコーダーの使い勝手はある程度録り貯めてみてわかると思うわけですが、我が家のPS3はtorne購入時点で残量20GB強。30分アニメ番組数本しか録れません。やらなくなったゲームをアンインストールしても44GB程度でした。そこでこの機会にHDDの換装を実施。気持ち的に現行モデルに負けない320GBか500GBにしようとお店(ドスパラ)に出向き、価格差などを考えて、WDの500GBモデル、WD500BEVTをチョイスしました。7,000円弱でゲット。PS3につくのは2.5インチの9.5mm厚タイプ、S-ATA。3Gbpsのものはジャンパーで1.5Gbpsに固定した方が良いらしいですがジャンパーついてなかったのでとりあえずそのまま投入。いまんとこ普通に使えてます。WDのお家芸である節電機能のせいかゲームで時々つっかかるという書き込みもみかけましたが、そこらへんは未検証です。
バックアップは16GBのUSBメモリで足りました。ファーム自体は本
体のフラッシュメモリにあるのか、HDD交換して電源を投入するとフォーマット画面が出てきて、フォーマット後は普通に起動。バックアップデータをリストアして完了。割と簡単です。1TB、2TBと欲しい人は別ですが、現状640GBまでなら内蔵を換装する方が色々と便利じゃないかと思います。レートの高いBS/CSは録れないので、500GBでも実用上は充分な人が多いのではないかと。
普段、PS3はプロジェクターにしかつながっておらず、気合いいれて映画みたりゲームしたりする用なんですが、しばらくは食卓前のテレビにつなぎかて、普段の録画視聴に活用してみようと思います。