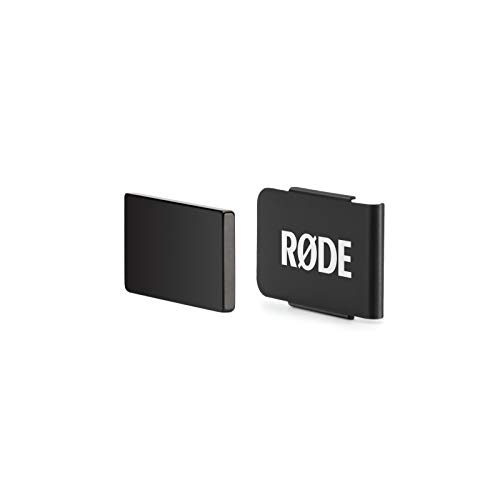戸建て新居にドアホンを設置しました。業務の宅配便が山ほど届くので、それを効率的にかつストレスなく受け取りするための投資です。
ニーズとして、
- 2階建てなので2階にいる時もとれるようコードレス子機がある
- スマホ連携で外出先でも受け答えできる(置き配指示など)
- 宅内ではスマホを子機にもできる
- 静止画または動画で来客を撮影、録画できる
という条件を設定。スマホを子機にできれば1番目はいらないかという考えもよぎりましたが、過去に実家でPanasonicのコードレス電話で同様の機能付きのものを導入したものの、アプリが不出来で実用レベルでなかったこともあり、やはり専用子機があった方が秒を争う受け答えには手早いだろう、と。
また録画機能は今のアパートに既設でついており、来たのがどの業者か判別つくと地味に便利だったりするので今回も条件に挙げました。
まぁドアホンなんてPanasonicかアイホンかみたいな寡占状態で、特にスマホ連携を条件にすると自ずと候補は絞られます。
結局選んだのはこちら。
PanasonicのVL-SWH705KLです。購入時点でスマホで宅外からビデオ通話ができるのは705シリーズと505シリーズのみ。画面が7インチと5インチという違いと、より新しい505だと室内親機にカメラがありスマホや別宅に設置した親機同士でビデオ通話ができるという点が違いです。同居人が大きい画面が良いというので705になりました。二人暮らしなのでドアホン使って会話するニーズはないですし。
また705にもコードレス子機の有無とセットの玄関子機のバリエーションがあります。玄関子機は型番末尾KSがアルミへアラインパネルの高級機(露出、埋め込み両用)。KLが一般的な露出設置専用サイズでプラスチックケースの標準モデルとなります。新居にはPanasonicのユニサスというポストが設置されており、露出設置フレームがついているのでKL一択でした。
パナソニック ユニサス ブロックタイプ 1Bサイズ CTBR7611SC ワンロック錠 表札スペースのみ ※インターホン...
また玄関門扉脇に設置した付属子機とは別に、玄関ドア脇にも玄関子機2として残置された音声専用子機があったんですが、残念ながら本機は音声子機非対応で、わざわざカメラ付きの子機に買い換える必要がありました。付属のものと同型も選べましたが、より安価なVL-VD561L-Nにしました。事前調査が足りなかっただけですが、予想外の出費でした。またこの子機はワイヤレスで単三電池6本で稼働します。配線を使わないので取付は簡単ですが、定期的な電池交換が必要になります。ワイヤレスなせいか安いグレードなのかカメラ画質も本体付属のものよりもやや落ちる気がします。一方こちらはカメラ向きを調整することができます。付属子機は物理的には固定ですが設定でズームエリアを指定することができます。
固定は既設の音声ドアホンのネジ穴をそのまま流用できます(フレームは付属品に交換)。
■ハード周り
5インチと7インチで伝送解像度が違うかどうかはよくわかりませんが、まぁたぶん拡大表示されてるだけじゃないかなと。でもまぁタッチパネルとしても大きくて操作は楽な気がします。レスポンスはスマホほどサクサクでもないですが、じれったさはギリギリ感じないくらい。連携デバイスの登録/削除と設定が別の入り口だったりGUIはいまいち直観的ではない気がしますが、まぁ普段そんなにいじる部分ではないのでまぁいっか、という位。自宅内で親機か子機で来客の対応をする、という点においては至極普通に使えます。
惜しいなと思ったのはインターホンとして使うのにスピーカーホンとして強制着信ができないところです。ご飯コールなど返信不要で呼びかけだけしたい時に、聞き手が受話操作をしないとならないのが面倒かなと。
■スマホアプリ
自分のiPhone 11 Pro MaxとGalaxy Note 10、同居人のPixel4XLの3台をペアリングしてますが、Androidはちゃんと通知が来ないことが多いような気がします。まだそれほど来客がないので自分達で試した範囲の印象ですが。また自宅Wi-Fiにつながって子機として機能しているか、リモートかでも違うかも知れません。もう少し検証をしてみますが、ド安定とは言いづらい気がしています。
通常は通知からアプリを起動しますが、特に来客がない時でも自分でアプリを開いてカメラ映像を見ることは可能です。玄関先を見るリモートカメラとしても使えます。
追加検証:
どうも外出中にドアホンが鳴った時、端末がWi-Fiにつながってると接続できないぽいです(画面真っ黒)。スマホ側がNAT下にいるとダメ?まだ自宅でしか発生してないのでウチのNAT環境の問題かも知れませんが、、(外出中にちょうど来客がないと試せないのでまだ検証ケースが足りない)。
とりあえず「ピンポーン」と鳴って通知が出たら急いでWi-Fiを切ってからアプリを立ち上げる、ということをしています。これで通話も含め一応使えています。
追加検証:
その後、Wi-Fiにつながっていてもつながる時はつながる、という感じ。つながることも多いかな?しかし同居人のAndroidには通知がこないことがほとんど(たまに来るので通知がOFFになってるとかでもなさそう)。
いずれにせよ通知からアプリ開いて通話を開始できるまでのもたつきは、付属子機で応答するのに比べて何倍もかかるので、たいていの配達員さんはつながる前に宅配ボックスを見つけて庭の奥に入っていっており、カメラには誰も映らない、ということが非常に多いです(笑)。そして置き配がすっかり定着した世の中になり、あまり活躍の場がない気がしますが、それでも大事な配送予定がある時に待たずに外出できるのは安心感があって良かったなと思います。


![パナソニック Panasonic ワイヤレス玄関子機 VL-VD561L-N[インターホン ワイヤレス]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/biccamera/cabinet/product/3067/00000004149171_a01.jpg?_ex=128x128)









![PDA工房 RODE Wireless GO Perfect Shield 保護 フィルム [送信機/受信機用 2枚組] 反射低減 防指紋 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41HPWY2uPbL._SL500_.jpg)