NURO開通間近になった突然同居人が引っ越すとか言い出しました。まぁNUROの費用は家計に計上せずσ(^^)が経費として払う予定で黙って申し込みしたという経緯もあって文句もいいづらく、仕方なくキャンセルの方向で調整することに(屋内工事が済んでいるものの、調べた限りはまだ工事費とられずにキャンセルできるっぽい)。
とはいえ良い物件を見つけて実際に引っ越すまで少し時間もあるし、引っ越した先で高速は光ファイバー回線を開通できるまでにもタイムラグがあります。そこで速度が安定してかつ使い放題なモバイル回線を追加契約することにしました。現在のアパートに無料付帯されるD.U-Netは200Mbps回線で空いてるとほぼ200Mbps出ますが混雑すると10Mbps位まで落ち、ブラウザでWebサイトを見ていても明らかに「遅いな」という感じになります。幸いルーターがRTX1210なので、例えば落ち込む時間帯だけデフォルトゲートウエイを切り替える、とか特定端末だけそちら経由にするといった方法も簡単にとれます(実際に以前WiMAX2+ルーターでやってました)。
据置型WiMax2+ルーター L01で自宅のネットワーク速度低下を補う話
当時メイン回線のiPhoneがau回線だったのもあってUQ WiMAXをチョイスしましたが、今は主回線がdocomo。そうとなればすぐ思いつくのが5Gギガホにして4Gエリアで使い放題とするプラン。主回線に付帯させるデータプラスなら1,000円でデータ回線がもて、5Gプランにするので+1,000円増えるだけ、、、と思ったんですが、5Gカケホのデータプラスで使えるのは30GBという制限があることが発覚。一時断念しました。さすがにもう1回線5Gギガホを追加で+7,8千円はしんどいなと。
しかし、よく考えると現在の
・ギガホ2(iPhone)+データプラス(クルマ用ルーター)
の契約から、
・ギガライト(iPhone)
・5Gギガホ(自宅用ルーター)+データプラス(クルマ用ルーター)
の組み合わせに移行すれば、ギガライト+5G差額500円になるのでまぁ許容範囲かと。5Gギガホは5G圏外、つまり従来の4G LTEエリアであっても使い放題(2020年6月現在)です。また半年は1,000円/月割引きがあります。
いままでどちらかというとiPhoneよりクルマ用ルーターの方がパケット使用量が多かったんですが、さすがに30GBあれば充分ですし、超過後も3Mbpsは出るので実用上問題なさそう。また楽天MNOのサブ端末もあるのでスマートフォンとしてiPhoneでの通信量は更に減るだろうと。
また今のiPhone側のギガホ2を解約しても解約金は1,000円で済みます。
■ルーターはSH-52A一択
現在ドコモで5Gギガホが契約できるルーター機種はSH-52A一択となります。5Gスマホのテザリングでは自宅の常時回線としては使い勝手が悪いので、モバイルルーターとしてはかなり割高感ありますが仕方有りません。その代わり、スペック的に
- 2.5Gbps マルチギガビットイーサ
- Wi-Fi6
と自宅用としても見栄えする仕様となっています。基本持ち歩かないのでデカいのも問題なし。今ほぼ使ってないHW-01Lも処分できるので足しにできます。
この製品はほぼ店頭在庫をおかない予約商品でしたが、幸い最寄りのドコモショップで1店舗だけ在庫があるところがありゲットすることができました。ドコモショップ取り分であるところの「頭金」が思いの他が高く(1万円以上)、8万円台半ばと言われ一瞬キャンセルしてオンラインを待とうかとも思いましたが、まぁ他にプラン変更とかまとめてやりたいし確認しながらしたいこともあるしと手数料だと思って諦めました。というか最初から手数料だと言えばいいのにと思いますが、そしたら余計に(人件費というものを理解できない)人が来なくなるんでしょうね…
音声オプションは付加できた
ちなみに音声オプションは付加できました。データ端末に音声オプションつけても意味ないと思われるかもしれませんが、
- 5分通話無料オプション 700円
- 5Gギガホ音声割で1年間 -700円されて実質無料
- みんなドコモ割で5ギガホと(4G)ギガライトの2回線なので-500円x2される
- いずれ5G音声端末を入手したら音声も使える
ということで少しだけお得なのです。最初はSH-52Aだとつけられないといわれましたが、奥で確認したのちはOKといわれました(後述の件もありちょいと頼りない店員でした)。
■SH-52Aファーストインプレ
購入前に検索しましたがびっくりするほどレビュー記事が少ないですね。impress位でした。しかもコロナの影響で5Gエリアでの実測値もありません。かなり冒険でしたので、これから検討する皆さんの参考になればとできるだけ書いておこうと思います。
やはりデカいです。モバイルルーターで放熱口が空いてるとか初めてみました(ファンはなさげ)。それだけ5G、Wi-Fi6、2.5Gbpsの発熱がスゴいんでしょうね。実際普通においてあるだけでも結構熱を持ちます。素手で持てないほどじゃないですが、冬はカイロにもいいんじゃないかってくらい。とりあえず安定動作してほしいので大きなアルミヒートシンクにのっけてますw。
タッチ画面の操作はメーカーが違うHW-01Lとかなり似ている印象。docomo指示で共通設計なんでしょうか。HW系に慣れた人でもすんなり以降できると思います。
有線LANポート、しかも2.5Gbpsなのはいらない人にはいらない仕様でしょうが、個人的には歓迎です。従来の「より小型なルーター+クレードル」という形よりもフラットで出張カバンなどに詰めていくには良い形状だと思います。私はホテルでPCに入れて持ち込んだ動画をスマホやタブレット、Oculus Questで視聴するということをよくするんですが、PCもタブレットもWi-Fiだと割と詰まってしまいがちで、PCは有線でつなぐようにしています。これが2.5Gbps + Wi-Fi6でどれだけ快適になるか次の出張がとても楽しみです。
充電はUSB-Cポート。ただし充電器は付属しません(A-Cのケーブルは付属)。私は多ポート充電器を持ち歩くのでむしろかさばる1ポートはついてきてもいずれヤフオクするときに「充電器、ケーブルは未使用です」と書きたいために箱から出さないくらいなので、最初から付属していないのは合理的だと感じます。本体が高いので、「まだお金がいるの?!」と思っちゃう人はいるかもですね。
推奨されている充電器はドコモ製のACアダプタ07です。こちらはPower Deliveryには対応しているみたいですが、SH-52A本体側がどうなのかは不明。CT-2があるのでそのうち調べてみようと思いますが、なにせ自宅で常にフル充電なもので…
・常時給電使用について
自宅などの定点仕様で常時給電しようと思った時、利用自体は可能ですが、バッテリーを外しておくとか、満充電にしない「いたわり充電」的な機能があったりとかはしません(少なくとも設定画面に項目はありません)。常時フル充電はバッテリーの寿命を縮めるわけですが、本機の場合はあまりそこに配慮がないようです。そして電池が劣化した場合自分で交換はできません。ショップで依頼するとしていくら、何日かかるのかは不明ですが面倒であることは確かでしょう。
ただ理由は不明ですが現状充電器つなぎっぱなしで充電が89%で止まってしまいます。抜き差ししたり充電器、ケーブルを変えてみても数秒で赤ランプが消えてしまいます。説明書にはエラーの時は点滅するとなっているのでエラーではなく仕様なんでしょうか。今の使い方なら結果オーライなのですが、設定項目が見当たらないので、逆に100%まで充電したいときはどうすんだろ?と思っています。
・管理ページの不具合
ブラウザから管理ページにアクセスすると再読み込みループに入って進めなくなることが多々あります。ブラウザやデバイスを変えても同じ。動的情報の読み込みに失敗してリセットされてる感じ。ログインボタンを連打してなんとかログインしてもリロードで未ログイン状態に戻ったり。こうなると本体を再起動するしかなくなります。再起動直後はちゃんと使えるんですが、またいつのまにかダメになってる、という感じ。ファームウェアで直るといいんですが。
■5Gベンチはまだできず…
すみません、これを期待してる方がもっとも多いと思うのですが、インプレスの記事と同じで、現状手近なエリア(というかスポット)が近くになく、羽田空港とか人の集まるところに行くのも憚られるので未計測です。神奈川県は5Gが使えるドコモショップすら1件しかないし、横浜スタジアムは「客席付近」となってるので、いっても入らなければ5G電波をつかめないかもしれません。
4G+については自宅が公式マップでいうピンク(1.7~1Gbps)ではなく黄色(938~250Mbps)のエリアで、2.5Gbps接続のPCから下りが300Mbps弱くらい。上りはやはり振るわず20Mbpsとかいっても30Mbpsというところです。pingも40msくらいあります。うちはアパートの無料付帯回線が200Mbpsなので、下りでは勝っても上りとレイテンシーでは大負け、という感じで、特に自宅回線が遅くなる時間帯に4K動画を見る、とかいう時のバックアップにはなる感じですが、完全に置き換えずにやはりRTX1210のフィルタ機能で端末(目的)別、時間帯別で使い分けるレシピをよく練らないとなぁという感じ。
Wi-Fi経由のスマホ計測ではWi-Fi6の効果は感じられて下り250Mbpsくらいは出てる感じ。Wi-Fi5だと160Mbpsとかに落ちます。「Wi-Fi5の理論値にすら届かないから同じ」という感じではないですね。同様に2.5GbpsではないPCだともっと遅かったりします。
(すべてspeedtest.netにて計測)
2020.06.29追記:持ち出してピンクエリアで計測してきましたが、トップスピードは250~300Mbpsといったところであまり変わらずでした。インプレスのレビューにある400Mbps台にはお目にかかれず。Wi-Fi6経由での2.5Gbps有線でも。
■5GプランではグローバルIPアドレスもIPv6も使えない!?
せっかく使い放題で自宅回線として使うので、サーバーアクセスやVPNにも使えるといいなと思いmopera Uをつけてもらうよう店頭で指定しました。しかし契約が進んだところで「5Gプランではmopera Uをつけられないようです」といわれる。アラジン(今もそういう名前かな?)をいじっていて気付いたようですが、「今さら言われても…」な状態です。「じゃぁグローバルIPアドレスで使えないってことでしょうか?」と聞き返したところ「お待ちください」とセンターへ電話。しばらく待たされた後、「5Gではspモードでも固定ではないですがグローバルIPをお使いいただけます」との返事。そんな大盤振る舞いあるの!?と思いましたが、ならmopera代もいらないしオッケーですと。しかし結果は間違いでした。がっつり10.始まりのプライベートアドレスが降ってきます。IPv6もなし。HW-01Lでは最初からspモードとmopera UのAPNが登録されていましたが、SH-52Aではそういうこともなくspモードのみ。IPv4/6を選ぶところもマスクされており編集も付加。ためしに自前でIP4&6のAPN設定を作成してみてもダメ。とりあえずspモードでもグローバルIPがつきますというのはガセでした。
もしかしたらmopera Uがつけられないという方も間違いではと期待して151に電話。マニアックな質問なので専門部署にまわされた挙句、判明したのはmopera Uも付加不可。現状、グローバルIPアドレスを5Gプランで使う方法はない、と断言されました。「店員が間違った案内をしたので後はその店舗と相談してください」と暗に返品してくれというニュアンス。そんなぁ…。
失意のあまりIPv6のことは聞き逃してしまいました。これも謎です。公式サイトではとっくの昔にspモードでもIPv6使えますよと書いてあるくせに、iPhone含めIPv6が降ってきた試しがない。「接続先設備によってはIPv6アドレスが割り当てられない場合があります。」との一文があるのでエリアによっちゃうんでしょうかね?
■アクセスポイントとして使うには難アリ
ちょっとマニアックすぎて誰の参考にもならないかもですが、せっかくWi-Fi6がついているので、自宅の既存LANに組み込んでWi-Fi6アクセスポイントにしてみようとトライしてみました。ざっくりいうと、
- SH-52AのLAN IPアドレスを自宅LANセグメントに属するものに固定する
- DHCPサーバー機能をOFFにする(自宅ルーターが担うため)
という手順。しかし結果としてはうまくいきませんでした。SH-52AのWi-Fiにつながった端末が自宅ルーターからDHCPでアドレスをとってくれません。SH-52AのWi-Fiと自宅LAN間の通信ができてないっぽいです。プライバシーセパレーターやSSID間通信許可の設定を試してもダメ。たまにある「自分のDHCPサーバーでIPを配布した端末しか通信できない奴」ですね。SH-52A側のDHCPサーバー機能を有効にしてやるときちんとLANとも通信できますが、自宅ルーターとダブルDHCPサーバー状態になるのでよろしくありません。SH-52AのDHCPサーバーをメインにするには非力すぎます(例えばMACアドレスで固定IPを割り振る機能もありませんし、配布するゲートウェイを指定することもできない。DNSだけは2つ指定できました)。IPフィルターとかで許可をするにも、そもそもIPをアサインする前のパケットが通らないんだからどうしようもなさげ?
そもそもさすがにモバイルルーターだけあって電波出力を100%にしても自宅の端っこでは電波が弱くて役者不足となりそうなので、Wi-Fi6 APとしての用途も諦めました。
ホテルに滞在した時なんかにも純粋なアクセスポイントモードって結構重宝すると思うんですが、、というかHW-01Lとかにはあった(ゲートウェイが有線ポート固定だけど)んですが残念です。
あれもこれもできるからこの価格でも仕方ないっ!と勇んで買ったものの何割かはNGで割高感が増していきますorz。
■SIMロック解除は店頭預かりで1週間程度…
以前に一括で買ったHW-01Lを処分するとなればSIMロック解除しておいた方がよかろうと。ルーター製品は無料ではあるものの店頭でやってもらう必要があるとわかっていたので、一緒に持参してやってもらうつもりでした。SH-52Aも一括買いなのでこちらもやっておけば後々楽天SIMとかでも使えるかも、とか。
が、しかし「預かりで一週間ほど。受け取りだけでも来店予約が必要。」というめんどくさい回答。さすがに買ったばかりのSH-52Aをさわりもせず1週間も預けるのはつらいので断念。HW-01Lのみ依頼してきました。なお返却は宅配便もOKでした(送料は言われなかったので店持ち?)。SH-52Aのロック解除はまた次の買い替えで処分する時になりそうです。
■サービスが追い付いていない印象はあるが、ハードには満足
というわけで、mopera U(グローバルIPアドレス、IPv6)が使えないとかがっかりな点はありましたが、モバイルルーターとしてのスペックの高さはサイズの大きさというハンデを補って余りある魅力と感じます。
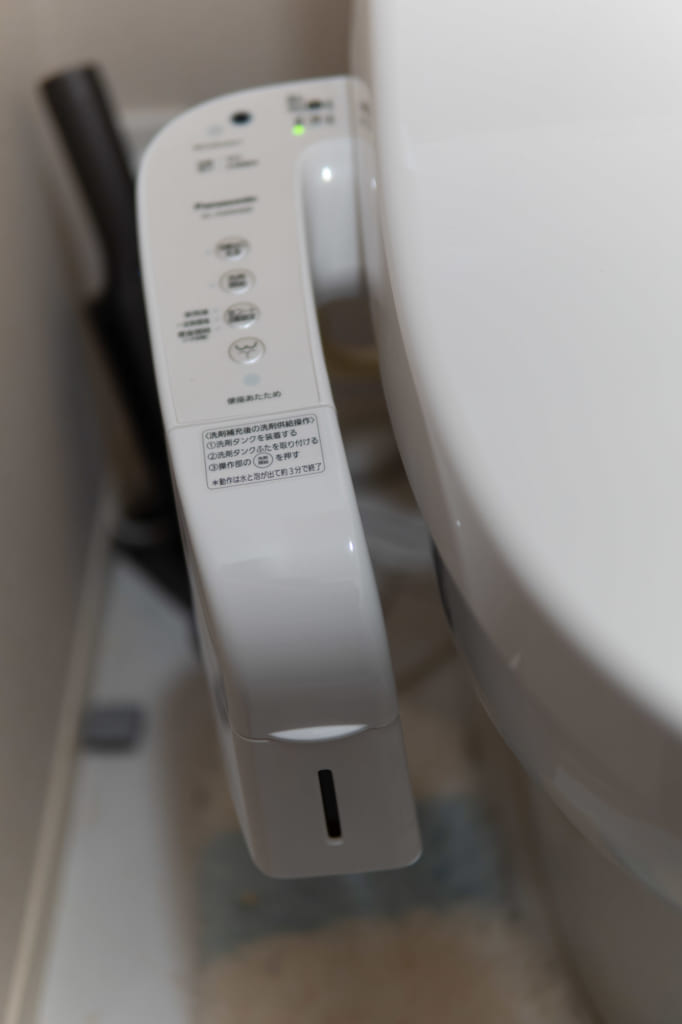

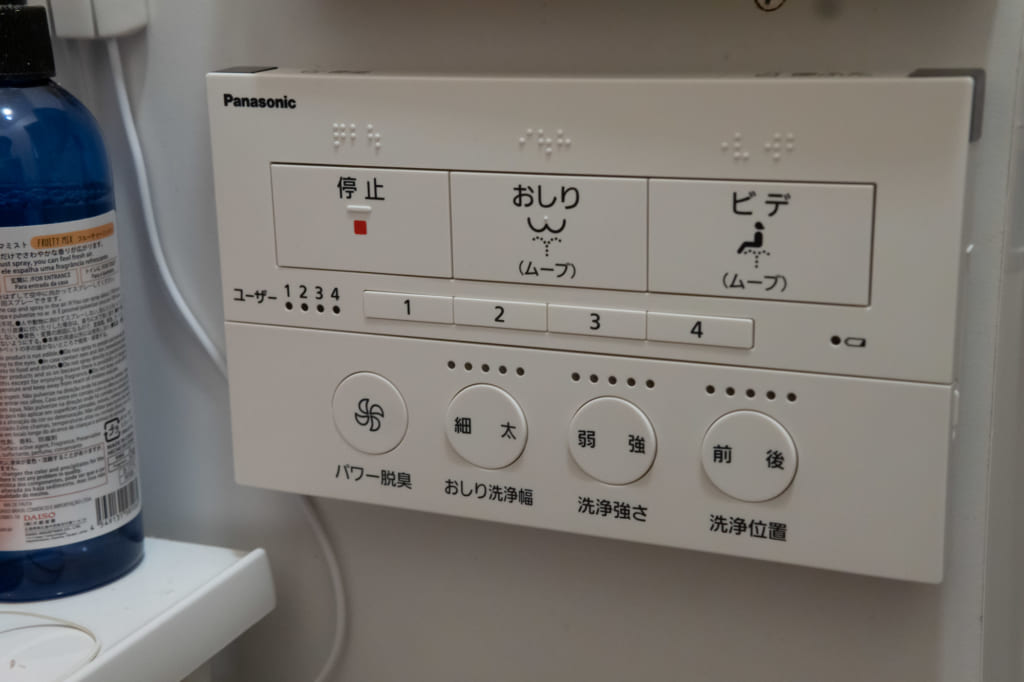




![[ソニー] REON POCKET専用インナーウエア ホワイト(L)](https://m.media-amazon.com/images/I/31+AyE39v8L._SL500_.jpg)
![[ソニー] REON POCKET専用インナーウエア ベージュ(L)](https://m.media-amazon.com/images/I/31dFrq5cmML._SL500_.jpg)





