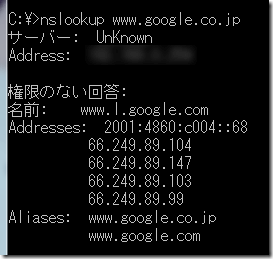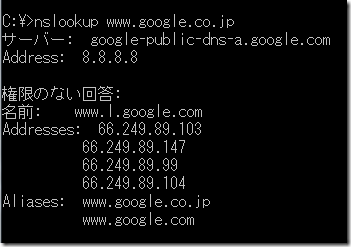VAIO P専用にマウスを購入。せっかくのスリムボディなのでBluetoothマウスを物色したんですが、これというのがなく仕方なくUSBワイヤレスアダプタのものに。Microsoft Explorer Miniを激しく気に入っているので、同じBlueTrackのMicrosoft Wireless Mobile Mouse 6000が候補にあがったんですが、競合メーカーの競合技術であるDARK-FIELDの「ガラス面でもOK」とのPRにも興味があったので、ロジクールのM905を買って見ました。MS 6000がピカピカのピアノブラックなのに対して、M905はつや消しのマットブラックでVAIO Pのカーボナイトブラックとマッチしそうだったというのも理由w。
ロジクールはトラックボールこそ自宅で3台も愛用中ですが、マウスは買うの初めてかも。周りの愛用者がよく故障報告をしているのでなんとなく信用がおけないイメージ。保証は手厚いので無償交換で済んでるケースも多いみたいですが。
M905のDARK-FIELD以外の特徴は、
- レシーバーが小さい
- ホイールがヌルヌルとカチカチを切り替え可能
といったあたり。MS 6000がヌルヌルオンリーなのに比べるとアドバンテージですね。
■マウス性能
ガラス面では試してないですが、概ね満足です。思ったところをビシっと指せる度合いは、BlueTrackのExplorer Miniを比べても遜色ないです。
形状はMiniよりも背が低いですが、MagicMouseみたいに手のひらを宙に浮かせる負担みたいなのは感じないです。
ホイールのヌルカチ切り替えはホイールの押し込みによるトグル動作です。これによって中ボタンとして使えないのは惜しい気がします。特にWindows7では中ボタンでタスクバー上のアイコンをクリックすると別プロセス起動、という割り当てがあるので(今んとこあまり使ってないですが)。
■モバイル用デザイン
レシーバー自体は売り文句どおり小さいのはGood。この手のUSBデバイスって、差し込んでみると奥までささらず金属部分丸見えってのが多いんですが、これはそうはならない点も評価したいです。
ただこのレシーバーをマウス側に収納するのにいちいちバッテリーカバーを開けないとならないのがいただけません。レシーバーが十分小さいんだから本体指しっぱなしでいいでしょ?って意図かも知れません。実際別途マウスに電源スイッチもついてます。でも、いくら出っ張り最小でも個人的にはレシーバーをPC本体に刺しっぱなしにはしたくないんですよねぇ。
マウスの電源スイッチはレンズカバーも兼ねていてわかりやすいち操作感も上々です。
電池は単三x2本入りますが、実は1本でも動きます。重量バランス的には2本入れた方がヨサゲ。
当初、3,500円くらいの安いBluetoothマウスを買うはずだったのが気付くと倍くらいするフラッグシップを買ってしまっていた訳ですが(←よくあること)、結果としては満足しています。