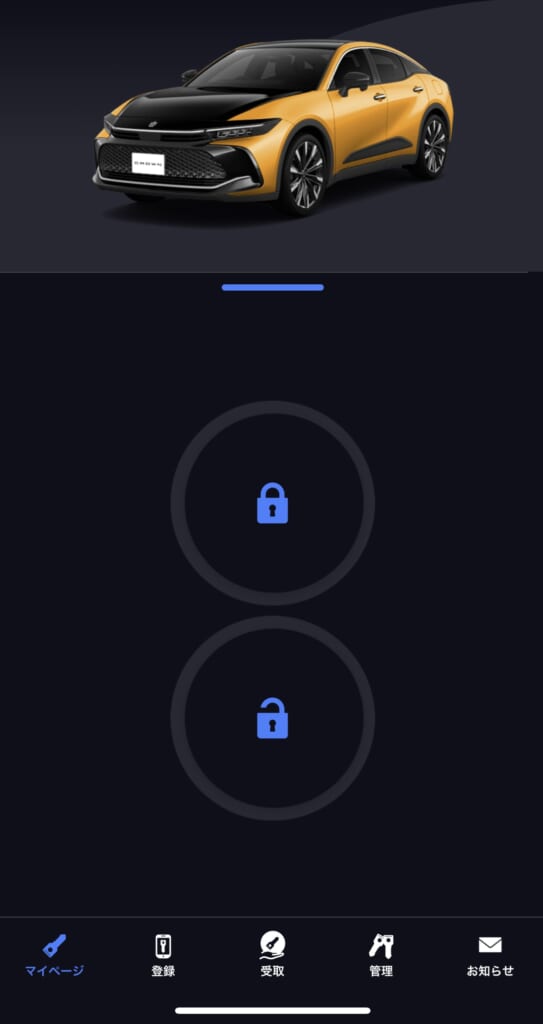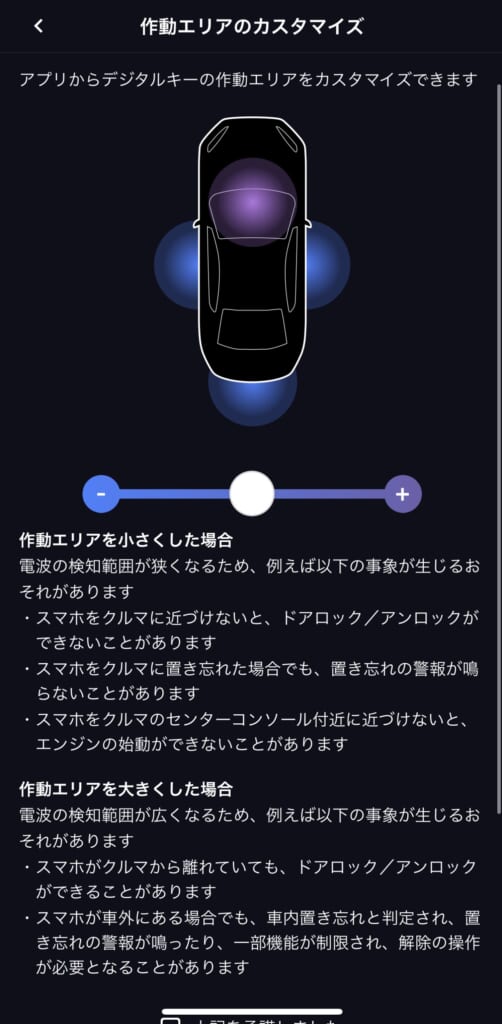ディーラーのアプリスタンプサービスが終わってしまい、洗車実質無料ではなくなってから自宅で手洗い洗車をしていました。クラウンもEXキーパーをしつつ普段の汚れは自分で洗う予定。バッテリー型のケルヒャーを使えば洗浄はそこそこ効率的にできます。
しかし特にクラウンは黒部分が多いのでしっかりと拭き上げないと水道水中のカルキ分が白残りしてみっともない(ウォータースポット)。またこれを放置するとイオンデポジットという塗装にダメージを与え凹んでしまう最悪の状態になります。
https://www.iic-shop.net/blog/?p=986#:~:text=%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%AE,%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A8%E8%A8%80%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
参考リンク 拭き上げは大きな吸水タオルを使うことで効率化できているといっても、クラウンは車体も大きくそこそこしんどいです。そこで効率化として考えられるのは2つ。
ブロワーで水分を吹き飛ばす
(カルキを含まない)純水で洗う(すすぐ)
どちらも理想をいえば最終的には拭き上げしたことが良いらしいですが、それでもそれが時短になるなら検討の余地はあるかなと。
■ブロワー案の検討
Youtubeで3Dプリンターでワイドノズルを制作して販売している方の動画をみてかなりそそられました。
マキタ #ブロワー #洗車 #ハイコーキ #kimo #NEODIT #エアダスター お待たせしました! 以前紹介した、洗車用のブロワーノズルですが視聴者様から販売の要望を多く頂いておりましたので、この度販売することにしました。 以前紹介した動画より、さらに改良を重ねたモデルになります。 対応するブロワーは6機種になります。また、マキタの充電式エアダスター用にも設定しています。 よろしければご視聴ください! Thank you for your patience! We have received many requests from our viewers to sell the blower nozzle for car washes that we introduced in our previous video. This model has been further improved from the previous video.
これならスポットではなく面で水滴を駆逐できそう。ブロワーもマキタの良いヤツから中華製(?)のお手頃モデルにまで対応してるラインナップでよさげ。直接ボディを擦らないので傷防止の観点からもかなり有効じゃないかと。
ただブロワーがマキタやハイコーキといったきちんとしたブランドは結構高い。本体はそんなでもないんですがバッテリーと充電器を別に買うと2,3万コース。安物なら1万円切ってたりしますが、どうせこの機会に手を出すならバッテリーが共通で色々な機器に使えるマキタ憧れます。また結局風量ショボかったらボディ全体にかけるのも結構時間と体力食いそう。ちょっとハンドリングは悪くなりますが、どうせ自宅でしか使わないので100v電源タイプもお手頃でいいかもなと思ったり。(100vタイプに適用できるノズルがあるか調べてませんが)。
あとこの方がノズルを自宅でせっせと製造されてらっしゃるようで生産数が限られてるぽいので、すぐ手に入らなそうだったので結局保留にして純水プランに決めました。
ブロワーはいずれ補助的に隙間の水を抜くとかにスポットで使うとかでもいいかなとか思っています。とりあえずは電動エアダスターはもってるので、そういうのでドアの隙間やドアミラー周りなどに潜んだ水滴を吹き飛ばすことから初めてみようかと。
■まずは純水器を導入してみる
ようやく本題。これから暑くなると洗車は時間との闘いになってきます。 シャンプー洗いや拭き取り作業が手間取ると水滴がどんどん乾いてしまいます。また炎天下での作業量、時間そのものを削減したい。ということで、あらかじめ白残りの原因になるミネラル分を純水器で抜いて使って、拭き取りより先に乾いてしまっても、あるいはそもそも拭き取り工程を省略しても心配のない形にしていこうと。
購入したのはこちら。
比較したのはこちら。
前者は5L、後者は10Lなので価格性能比は高いんですが、その分、消耗品の樹脂もたくさん必要ですし、庭においとくだけとはいえデカい。そしてなにより気になったのは、後者は樹脂を小さな口から直接流し入れ、本体をトントンして馴らしながら詰め込んでく作業がめっちゃ大変そうという点。前者は大きな口に袋に入れて詰める形っぽい。性能的にどちらに優位性があるかまではわからないですが、なんとなく下から入れて上から抜ける構造の方がしっかり樹脂を通過してくれるイメージもあります。
事前に自宅周辺のミネラル度がさほど高くないことを水道局の統計値で調べたり、自分の洗車頻度も考え、使い勝手やコストを重視して5Lでいくことにしました。(ただ10Lなら倍の水を純水化できると思うので、多く購入する必要はありますがランニング単価はかわらないと思います)。
多くの純水器の例に漏れず購入したものにも水質計(TDSメーター)が付属しています。水の電気抵抗を計測して、不純物がなければ電気が流れないので0ppmとなります。ミネラル分が残留しているとそれなりに電気が流れてしまいます。
自宅の水道水は82ppm 純水器を通した水は0ppm! とりあえずきちんと0ppmに落ちてくれました。時々これをチェックして0ppmまで落ちなくなったら樹脂の交換時期ということになります。
なお購入時は本体内に予めセットされた分に加え1回分の交換樹脂が付属しています。交換樹脂を単体で購入すると2回分でこちら。
まぁまぁしますねー。公式では1カートリッジで12回洗車できると言っています。月イチなら1個1年。2個付属してくるので2年保つ計算になります。とはいえ車種や最後のすすぎだけ使うのか、最初の砂埃落としにも使うかだけでも倍は違いますし、どういう基準なんだろ。10回洗車できたとして水道代別で800円/回。コイン洗車も水道水なら600円位でしたっけ。まぁ拭き上げの手間が本当になくなるなら悪くないかも?
■初期テスト
ではGWで帰省していい感じに汚れたので早速洗車してみます。EXキーパー後、まだ一ヶ月目洗車(補強)が終わってない段階です。
まずは最高に手抜きして「高圧洗車で砂埃を落とすだけでどれだけ綺麗にできるか?」の検証です。
ケルヒャーで水をかけただけ。拭き上げもせず、この写真の状態で放置。ただしこの後で出かける用事があって走りました。暗くなってしまったのでチェックは翌日へ持ち越し。
そして翌朝。おぉ、遠めには結構綺麗になってます。急に仕事先に乗っていくことになった、みたいな時はこれをするだけでもかなり違うかも!
とはいえよ~く寄ってみるとやはりそれなりにシミはあります。一番右のなんかはヤバそう。今日は改めてシャンプー洗車してやろうと思います。
本命:シャンプー洗車後の純水洗車、拭き上げ無し
こちらはいい感じに綺麗になりました。ミネラルの白残りは見当たりません。拭き上げをまるまる省略できるなら結構な時短になります。またジャンボ拭き上げタオルは拭き上げ自体はそこそこ効率化できるんですが、洗濯が微妙に手間。家族からは他の洗濯物を一緒には洗いたくないが、1枚だと無駄な気がすると言われました。どうせ使うならケチらず2枚使ってさらに時短してしまった方がいいかも。でもまぁ純水で拭き上げ無しで充分綺麗になることがわかったので、今後はジャンボタオルの出番も少なくなりそう。乾かすヒマすらない時くらいですかね。
まとめ
今後色々なパターンを試して自分の納得度と手間/時間のバランスを探っていきたいと思います。
Lv1. 純水ぶっかけて放置(砂埃が残る可能性があるので拭き上げNG)
Lv2. シャンプー洗車後に純水すすぎ、拭き上げなし
Lv3. キーパーラボでミネラルオフopつき手洗い洗車(3,4ヶ月毎)
位の組み合わせで回していければなと思っています。とにかく時間がないけど最低限綺麗にした時にLv1。普通に時間がある時にLv.2。水弾きが悪くなってきたら、トレッサ横浜に買い物にいったついでにLv3依頼、もしくは自分で施工。
あとは実際10回以上洗車しても0ppmを維持できるのかどうかですね。
注意点としては樹脂材が乾燥に弱いので、使い終わったら適度に水圧は抜きつつも中に水は残った状態にしておく必要があります。この製品には入水、吐水の両側にコックがついていて口を閉じておくことができるので、水をたっぷり入れた状態で口を締めてしまえばホース自体は抜いて他の用事に使っても大丈夫そう。毎回これは忘れずにしたいと思います。
またせっかく純水が利用できるようになったのでクルマ以外にも家のガラス掃除とかにも使ってみたいですね。







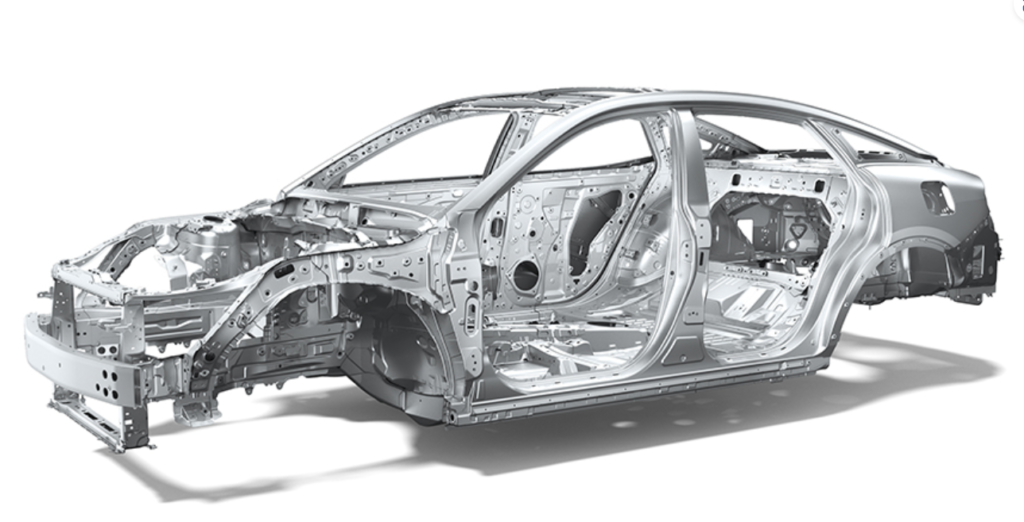
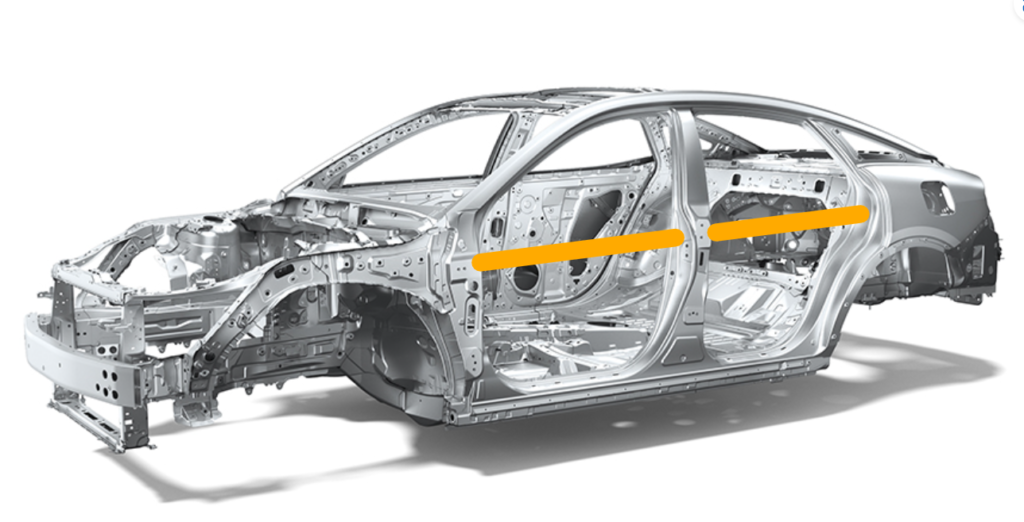
![TRD GRドアスタビライザー トヨタGR86[ZN8]用 MS304-00005](https://m.media-amazon.com/images/I/31vtiEa7beL._SL500_.jpg)