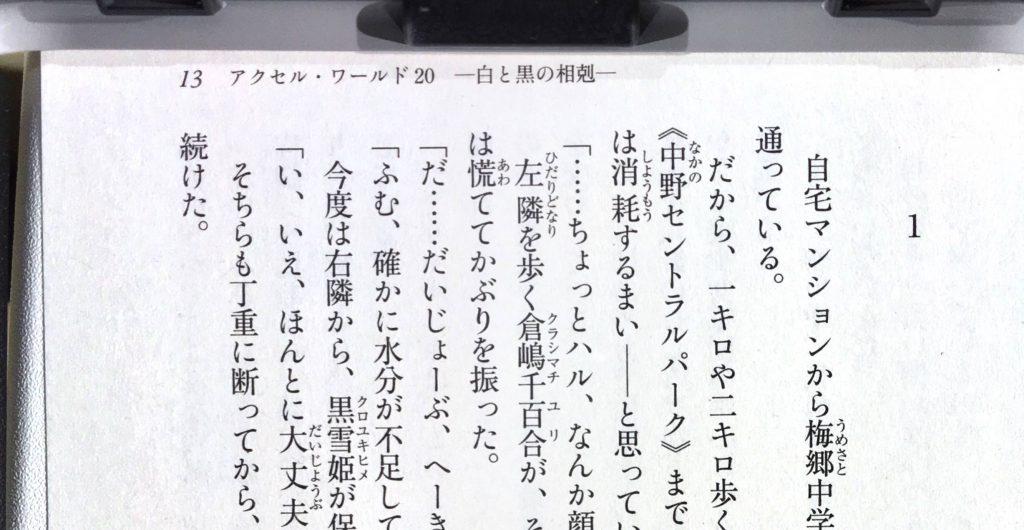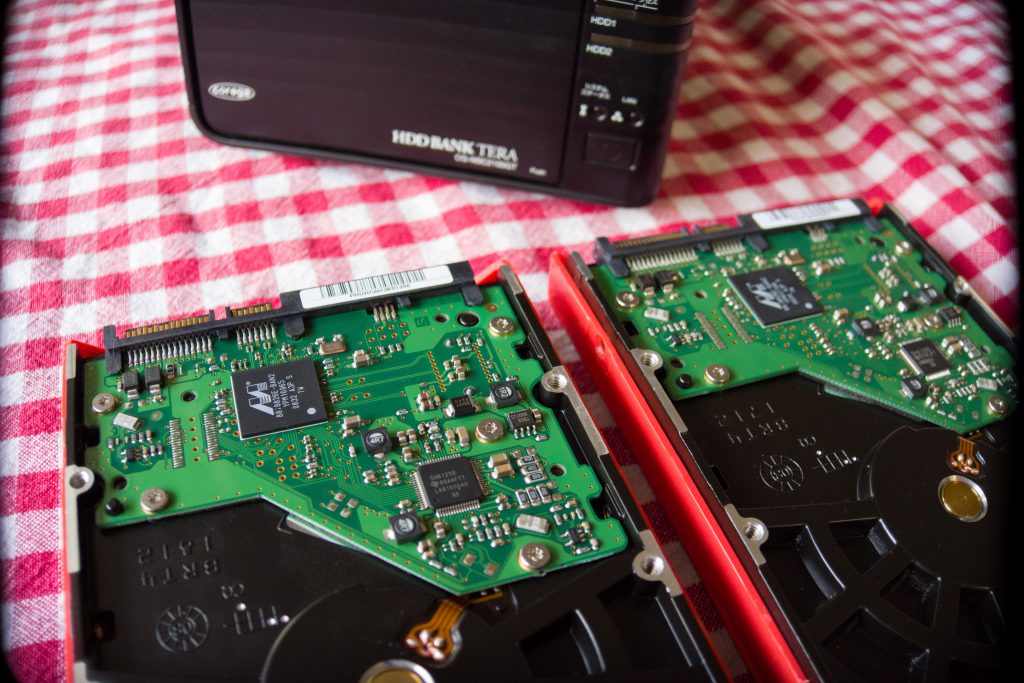最近めっきり音楽を聴く機会が減り、CDもあんまり買わなくなりました。たまーにハイレゾ楽曲をオンライン購入するけど、それもまぁあんまり聞いてなかったり。それでも当期アニメのOP/EDとかをもう少し聴きたいとか思いつつ、買う程でもないしとか悶々としてたり。DMMレンタルの枠が余りまくってるけど、なんかもうCDのリッピングが面倒くさい。あとiOSのミュージックアプリがどんどん使いにくくなってたりとか(iOS10で改善されるといいすね)。
で、まぁ定額配信サービスに月1,000円払えばいっそスッキリするかなと思い、課金してみることに。Apple Music(以下Apple)もGoogle Play Music(以下Google)も試用はしてたんだけどあんまり聴くもん(アニソン)なくて課金には至らなかったんですが、最近はApple意外は割と充実してると聴いて(ただまぁないレーベルはあいかわらずないし、サントラやゲームミュージックも壊滅的なのはおんなじなようです)。
で、ググるとアニソンが比較的強いとされてるのがGoogleとAWA。スマフォアプリをざっと触った感じAWAはなかなかサクサクしててよさげ。ただ以下の機能が魅力でGoogleにしてみました。
- ロッカー機能で手持ちの楽曲もアップロードしてライブラリに統合できる
- 将来的にYouTube Red(広告無し)もついてくる
- ファミリープランがある
など。特にマニアックなアニソンやゲームミュージックが多いσ(^^)的にはロッカー大事。YouTube Redはどのみち単体でも契約する予定だったので割安感ありますし(現状VPNサービスでアメリカのIPから手続きすれば既に使えるって話もありますが本当なんすかね。試してみたい)。また同居人が興味を示したらファミリープランにするのもいいかなとか。
■Chromecast対応
GoogleとAWAのその他の強みとしてChromecast対応があります。Apple MusicをAppleTVなどにAirPlayした場合、MacやiOS端末経由の再生になるのでバッテリー負荷などがありますが、ChromecastはDLNAのクライアントとコントローラーみたいなものなので、スマフォで選曲してChromecast互換機器に再生指示を出した後はスマフォは関係なくなります。またAndroidやChromeブラウザからも流せるのが便利。
我が家にはもともと複数台のChromecast端末があります。4K AndroidテレビのX9300cとWi-FiスピーカーX88です。あと普通にChromecastも第1、第2世代ともあります。
3月に買った4KテレビのSONY X9300cは標準でChromacastクライアントになります。スピーカーもハイレゾ、アップスケール対応でGoogle Playの320kbps MP3でもそこそこいい音出ます。音楽を聴くのに画面が点いちゃうのが無駄なのがたまにキズ(テレビのリモコンから画面消し操作は可能ですが)。またたまに再接続が効かなくて操作を受け付けなくなり、結局テレビ側のリモコン操作が必要になることも。(リンク先は現行モデルのX9350Dです)
こちらも同社のWi-Fi対応ハイレゾスピーカー。お仕事の関係で実質タダで手に入れました(^^)v。専用アプリSongPalからスマフォ内やDLNAサーバー上の音楽を流せたりBlurtoothスピーカーになったりしますが、Chromecastクライアントとしても機能します。大きさの割にしっかりとした音が出ます。
先々、活用できそうなら追加で導入しよかなと思っているこはこの辺。
Chromecastの音声専用版。HDMI端子のかわりにアナログと光音声出力があるクライアント端末。TVの調子がどうにも悪かったらこれをAVアンプにつないで使うのもありかなと。
また、これまたSONYのスピーカーシリーズですが、バッテリー駆動型で初のハイレゾ対応機SRS-HG1もほぼ買おうかというモードです。ちょうどまたお仕事絡みでヨドバシポイントが3万円くらい貯まってるのでw。SongPal対応スピーカーが複数あるといちどに鳴らすことができるのと、帰省や出張にもってけるのが便利かなとか。店頭で試聴した感じ音質もまずまずで、BOSEのSoundLink Mini IIと競合で悩みつつ、やっぱBluetoothだけよりはWi-Fiでハイレゾまで鳴るこっちだよなぁ、と。音質はSoundLinkも捨てがたいんですけどね。
■共有テスト
たまたまみつけたdaiのアルバムでも。ひぐらし原作版のBGMですね。なつかしい。Google Music定額プラン契約して無くても試聴や単体購入はできるっぽいですね。なんか綺麗に貼れるWordPressプラグインがあればいいんだけども。
https://play.google.com/music/m/Bngwe66vn357ngi5oesydw5v3ye?t=Yours_-_daiMGraveyard