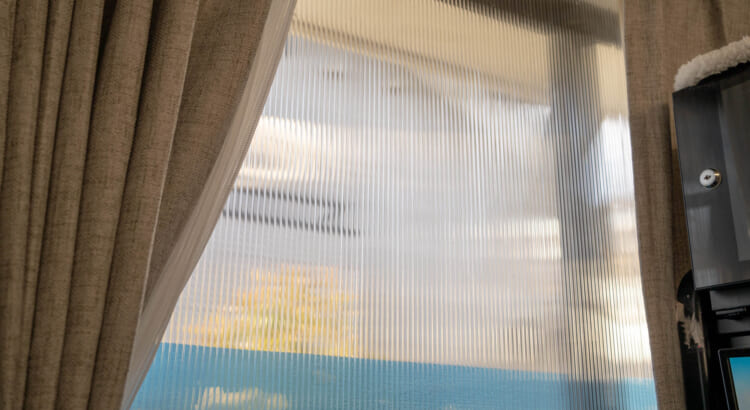■ヘルシオデリはちょっと手を出しづらい
先日、妹家族がコロナ陽性になり自宅待機となりました。実家が近いので買い出しなどは母親などが代行できるっちゃできるんですが、やはり高齢者をできるだけ陽性者に近づけたくはないなと思い、こちらでもリモートからできることをしてみました。
その時、先日買い換えて余った初代のホットクックを、次帰省する時に譲ってやろうと思って保管してあったのを宅急便で送り、公式のミールキット「ヘルシオデリ」で希望のメニューを3点選んで送ってやりました。ヘルシオデリはホットクック(やヘルシオ)で作ることを想定したミールキットの宅配サービスで、届いた材料をホットクックに入れて指定の加熱メニューを設定するだけで調理できるというものです。自分でも検討したことはあったんですが、やはり少々お値段が張るなという印象で躊躇していました。1メニューが安いもので2,3人前で千数百円前後、ちょっといいなと思うメニューだと2人前で2千円とかして、プラス送料がかかります。まとめ買いすれば送料が割安にはなりますが、冷凍庫の容量を考えるとそうそうたくさんは買えません。
またたまたまかも知れませんが(ちょうどお盆直前くらいだった)注文から配送まで1週間ほどかかり、結局コロナ自宅待機用緊急食材としては間に合わず、待機明け記念のごちそうみたいな位置づけに。妹宅では初ホットクックだったこともあり、簡単に料理ができてしまうことは好評でしたが、まぁ自腹では買わないよね、という感じ。
■「旬をすぐに」を知る
そんな折り、家電ウォッチの記事で「旬をすぐに」(以下、旬すぐ)を知りました。
全体としてはホットクック用ではないお手頃冷凍ミールキット宅配サービスです。398円、498円といったリーズナブルなミールキットが非常に多彩なメニュー提供されています。そのカテゴリの1つとして、「電気調理鍋キット」があるという感じ。ホットクック専用ではなく他社のかき混ぜ機能が無いものも含めて対応という位置づけのようです。現状10メニュー、カレー多めですが2〜3人前1,098円とヘルシオデリに比べるとかなりお手頃。ただしこちらも送料が気になってしまうのは同じ。やはり冷凍なのでまとめ買いもしづらいです。
でもまぁ自分でもホットクック用ミールキットを試してみたい衝動に駆られ、とりあえず牛すじカレーとコルマカレーを注文してみました。
で早速牛すじカレーを調理。ボックスの中身はこんな感じです。

業務用冷凍機で急速冷凍された食材が並びます。というか4つはカレールーの団子です(笑)。これをすべてと指定分量の水を電気調理鍋に入れて手動メニューで10〜20分加熱せよとの指示。他社はわからないですがホットクックは「沸騰後に指定時間加熱」という仕組みなので、20分でセットしても実際には10分くらいでかなり煮詰まる音がしてきたので止めてみたところ充分にカレーになっていました。ホットクック用ではないので、まぜ技ユニットの指定などはないですが、せっかくなのでまぜ有りで調理しました。

分量的には「2〜3人前」ですが、( ´)Д(`)用にこんな感じのお皿に盛り付けると2杯分かなという感じ。味は割とスパイシー(辛いもの苦手な人間の意見です)。でも牛すじも柔らかく美味しかったです。不思議なことに普段レトルトカレー食べると30分くらいで速攻お腹を壊す自分ですが(胆嚢摘出済み)、今回、日を変えて2回食べても下しませんでしたw。
ミールキットって食材を切らないで済む点では時短ですが調理時間は普通の料理と同じくらいかかる、というイメージですが、こちらは冷凍庫から出して沸騰時間+10分の放置で完成するので時間も手間もレトルト食品、インスタント食品を用意するのに毛が生えたような程度です。なんならまだご飯が炊けないくらいの速さ。感覚的にはスパゲティを茹でるくらいの覚悟で作れる感じです。それでいて割としっかり美味しい料理が食べられるのは魅力です。
配送も翌日発送されて注文日の翌々日には届いたので、ヘルシオデリよりも利便性が高いです。
惜しむらくはやはり送料ですかね。これがスーパーで買えたらリピ買い、ストック買いの射程に入るかなという感じ。せめてAmazonフレッシュのような宅配スーパーの枠組みの中でなら他の乾物や菓子類とあわせて送料条件を満たすことはできそう。「旬すぐ」メニューだけで送料無料になるまで買うと冷凍庫がパンクしてしまいます。「AI旬すぐ」というAIがオススメメニューを定期的にお届けするサブスクコースだと送料無料になるんですが、この電気調理鍋メニューを含めることができるのかはサイトを隅々まで読んでもよくわかりませんでした。一応AIが選んだメニューを手動で変更でき、基本メニューより高いものは差額上乗せになる、ところまではわかったんですがいまいち確証が持てず。
でもまぁ電気調理鍋用メニューにこだわらず、普通に冷凍ミールキットとしても比較的お手頃なので、そっちはそっちでいずれ試してみたくはあります。
■スーパーのミールキットをホットクックで加熱する
もう少しリーズナブルにミールキット生活をできないかと考えて閃いたのはスーパーなどで買えるようになってきた一般調理用のミールキットを適当な設定でホットクック調理する、という方法です。スーパーなら冷凍ではない冷蔵タイプのミールキットの見切り品がちょいちょいお値打ちに買えるので、たまに炒め物メニューを買ったりしてました。先日、「これを別にホットクックで調理したっていいんじゃね?」と思い、肉じゃがキットを買って来てつくってみました。冷蔵のものは大抵お肉は別売りなので別途調達します。自分は西友のものをよく買いますが、ここのはいつも調味液を全部入れるとかない濃い味になるので半分程度に調整。またホットクックは無水調理ができる程度に密閉度が高く水分が水蒸気として抜けにくいので、水加減も少し少なめに。メニューは普通に「肉じゃが」で。当たり前といえば当たり前ですが普通にできました。まだちょっと濃い目だったかな。調味液、水分、加熱時間のパラメーターはメニューによって加減がありますが、そこさえ見極めてしまえば手軽に作れるなという感触。また色々試していこうと思います。
![シャープ 水なし自動調理鍋 ヘルシオ ホットクック KN-HW16G-W 無線LAN対応 ホワイト系 [1.6L]](https://m.media-amazon.com/images/I/31q+8AFRQBL._SL500_.jpg)