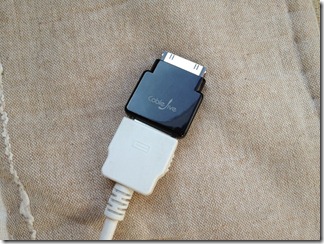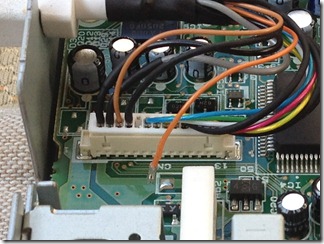実家のカァチャンが「毎朝もっと美味しいトーストが食べたい」と言い出した。後のトースター買い換え事件である。
元々使っていたのはNationalのマイコントースターで1,000Wのタイプ。ざっくりとリサーチした感じ、トーストを美味しく焼くには
- 強い火力で一気に焼き上げ、外はカリっと、中はふっくらを実現
- 均一に熱を伝えることで焼ムラを減らす
という辺りがポイントっぽい。ちなみにポップアップトースターも邪魔だからと却下。今あるオーブンをリプレイスする前提。
ならばと前々から興味のあったコンベクションオーブン(中で温風を対流させて均一で強い加熱を実現するオーブン)を薦めてみたのもの、SANYOも既にアレだし現行機種があまりない。ではオーブントースターで今より火力があるものをと探してみると、上位機種は1,300Wのものがぼちぼち売られている。よく別のことをしていて焦がしてしまう我が家では、マイコンタイプ(メニューボタンがついてるもの)がよかろうということでTIGERのKAE-S130-RGを推してみた。が、これも却下。とにかく黒がいいらしい。多少性能が落ちても黒は譲れないと。いつのまにか「美味しいパンが焼ける」よりも「キッチンをオシャレにしたい」に目的がシフトしていますw。
結局カァチャン自分でエイデンいって見つけて来たのが東芝のHTR-H6。1,200Wながら、フロントドアがミラーになっていて、熱を外に逃がしにくいのだとか。マイコンタイプではなく、温度とタイマーつまみだけで調理するタイプだったのでσ(^^)は反対したのだけど、結局デザインの勝利。確かに隣の日立の電子レンジと同じ、フロント黒で、サイドがシルバーで並べて見ると違和感がない。
■ハード面
操作パネルがサイドにあるタイプは本体が横長になってフットプリントが広がるのであまり好きじゃない(どうせ上にはなにも置けないので)のですが、今回に関して言えば手前にシンクがあってやや遠いので少しでも低い位置に庫内があるのは結果オーライという感じ。
気になるのは本体がとても軽量な割にタイマーのつまみが固い点。天板を左手で押さえながらグっと回す感じ。これ余熱がある時にやると危ないw。片手でダイヤルがさっと回せるように、本体をどうにかして固定しようかと思案中です。
■さてお味は?
価格.comのレビューや口コミをみてると、やたら「奥の方が先に焦げて手前が生焼けで糞」という指摘があり、初回はとりあえず気にしながら本体パネルに書かれたパラメーター(240℃、3分)でセット。案の定タイムアップ前に焦げて来たので中断。ただし奥だけという偏りは見られず。まぁ4枚焼けるところを1枚だけ(市販の4枚切り)でしかもレビューを気にして一番手前辺りにセットして置いたからでしょうか。
確かに今まで実家や自宅(こちらも1,000W)で使っていた物よりも表面がカリッしています。バターを塗って割ってみるとむぁっと水蒸気が。おぉ、なんかこういうのリアルで見るの初めてな気がする。あと表面温度が高いのかバターが塗りやすかった印象。そして味、というか食感も確かに美味しい。
今晩妹がホームベーカリーでパンを焼いてくれることになっているので、明日の朝は更に美味しいトーストが食べられるかも知れません。
とりあえずパネルに書かれているパラメーターはあまり参考にならないことがわかったので、適切な温度と時間については試行錯誤が必要そうですが、現在Amazonで5,000円強で買えるものとしてはコストパフォーマンス良い気がします。なんだか自宅も買い換えたくなってきた(多分自分ならマイコンタイプのTIGER)。